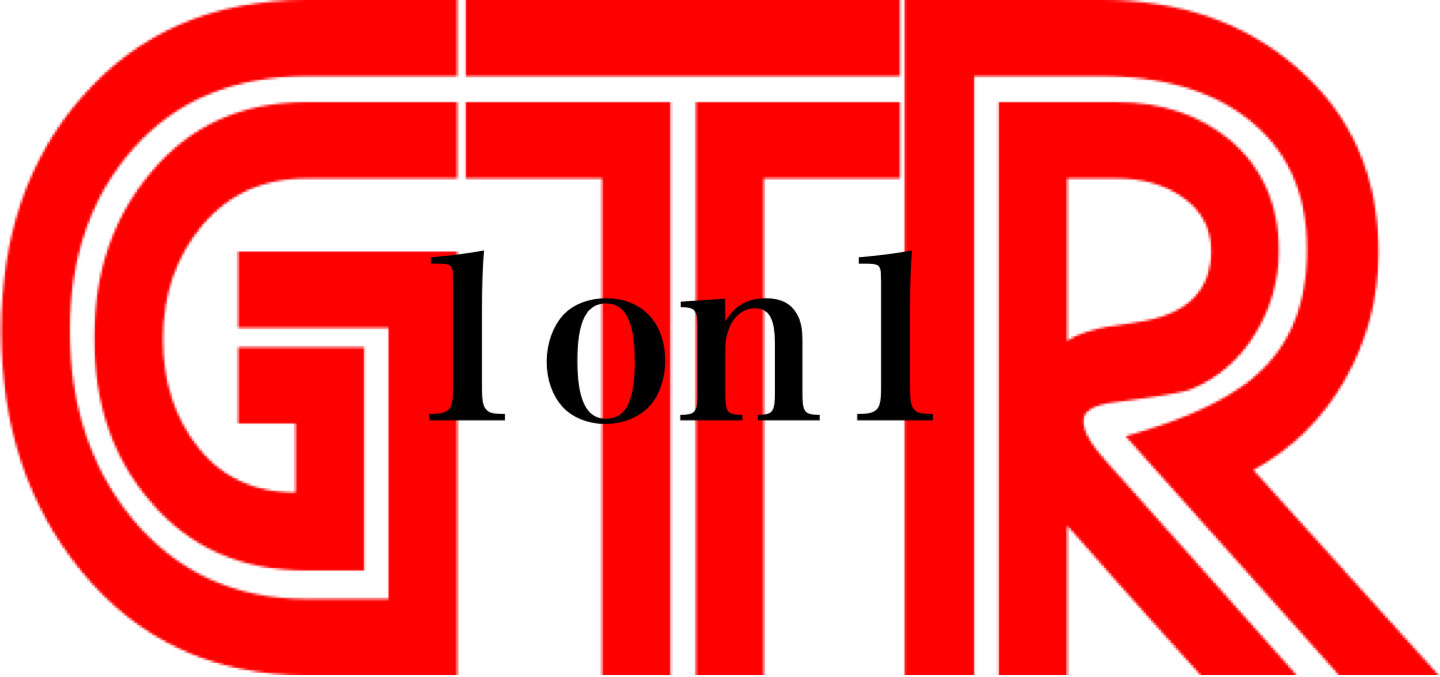夜馬裕と若本衣織——この二人がタッグを組んだ怪談集と聞いただけで、怪談ファンなら涎が出てくる一冊である。
ともに長尺で、練られた構成でオチが予測できず、一度では終わらぬどんでん返し。常に大ネタと言うべき濃密な怪談をストックしていて、怪談語りでは邪悪な内容に反する眩しい笑顔を携えて、獣に追われた獲物のごとく受け手を翻弄する。
体験談をひとつの壮大な物語として昇華させる力にとことん長けた両名の競作ともいうべき本書は、夜馬裕氏の提案により、「異界」というテーマで怪談が統一され、話の舞台も七つに設定されている。
実話怪談という、聞き取った話のリアルさといかがわしさ、語り得ぬ余白という部分に恐怖の質が顕れる歪なジャンルを、夜馬裕氏はときに老若男女が恐怖を楽しめる「ホラー」として還元する間口の広い仕事をするが、本書もまたそのような一冊であることは、タイトルや構成を見れば一目瞭然だ。
異界という漠然としたイメージの、それでいて体験談としては取材が難しそうなテーマを、「神隠し」という概念で纏め上げたのには、思わず膝を打った。
なるほど、神隠しの話だから、こんなくも怖くて、頁を捲る手が止まらないのか。
生まれて初めて「神隠し」という言葉を知ったのは、いつだろうか。
筆者は『ドラえもん のび太の日本誕生』だったと記憶しているが、神隠しには土俗的な響きと民話のイメージが醸し出す気味悪さと、時空を超えてしまうSF的な不気味さの両方が含まれている。
神という不可知の大きな存在に運命が理不尽に操作されること、元いた世界から条理なく切り離されて、放り込まれた先の世界で自身が存在せねばならないことが同時に起こり得る神隠しという現象は、時として「死」よりも恐ろしいのではないか?–と感じずにはいられない。
死はわたしたちの命の終わりとして認識されるが、神隠しという消失としての死は、終わりの先、この世界の向こう側にある異界への入り口として機能する。
死の先にある、死より怖い、わたしたちの想像を超える何かの気配というものを、夜馬裕・若本衣織の両氏は「神隠し」という定番かつ普遍的な概念を見事に扱うことで、手に汗握る恐怖の娯楽として蘇らせたのではないかと思う。
今回収録された15作は、山林、海川、史蹟、旅宿、路駅、市街、家屋と、手付かずの自然にはじまり個人の閉じられた日常空間までが順番に章立てされている。
序盤の山林や海川の章はフォークホラーとしての神隠しが描かれているが次第に雲行きが怪しくなってきて、史蹟の章では時間が歪み、旅宿の章からは空間そのものが変容する。
路駅の章に登場するロッカーやトイレは異次元空間に繋がっていますよね、としか言いようがなく、特に若本氏の「彼方にて」「午前八時十五分」「不正解の扉」は移動し続けることと、移動にあたりその境界に位置する扉を開ける、という行為の反復が話の軸となっており、開けた扉の先にあるものの異様さに息を呑む瞬間が幾度も訪れる。
扉の先に広がる景色の幻想怪奇極まった描写に圧倒される一方で、扉を開けることで【元いた世界から遠ざかる/元いた世界に近づく】ことになる際の、扉を開けるという選択肢の正解と不正解には、因果応報や法則性を見出せない。
「扉を開ける」という行為のよるべ無さと、その先に待ち構えるモノへの恐怖は背中合わせだ。
しかし、もしも自分がこれら怪異譚の体験者たちのような神隠しに遭ったとしたら、やはり同じように扉を何度も開けてしまうのだろう、とも思う。
本書を読んでいる時、怪談としては長めの一話一話を、手に汗握る不安な展開ゆえに先が気になってしょうがないという気持ちで一気に読まされた。
捲る頁の一枚一枚も、わたしたちにとっては異界へと繋がる扉なのだ。
これを開けずにはいられない。