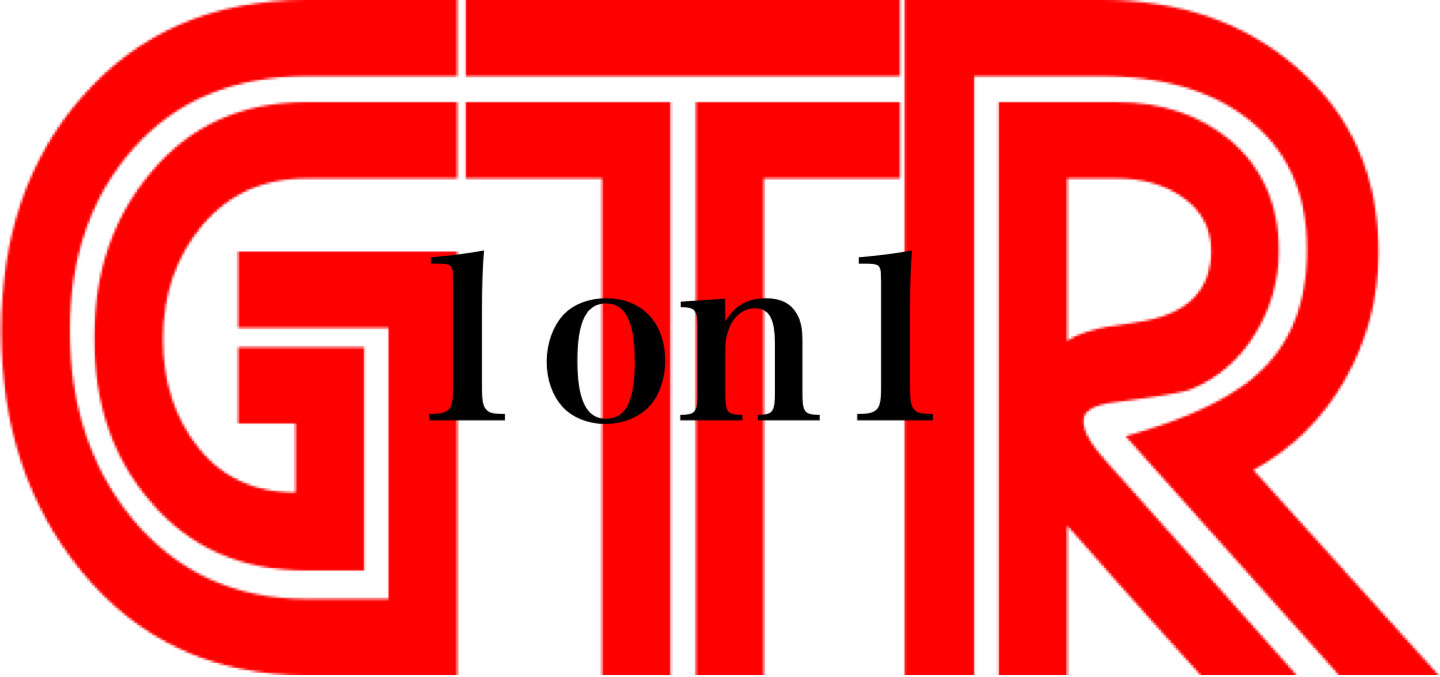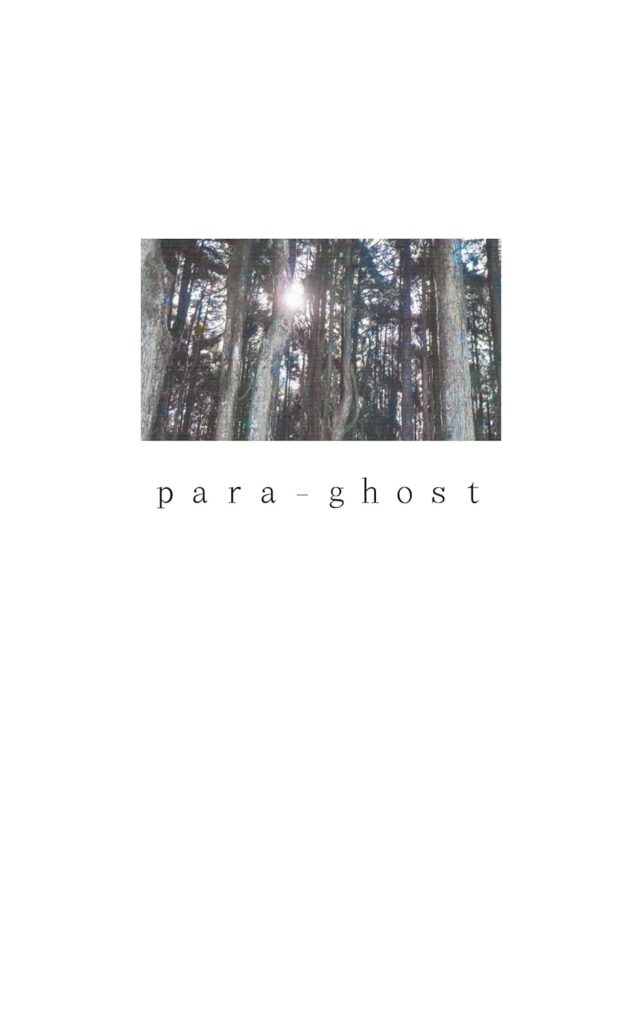
眼科で検査を受ける際、測定機械を覗くといつも同じ画像を見せられる。
空と草原が広がる景色の中央に一本の道路が伸びていて、その先には赤い気球が浮かんでいる。
誰もが一度は目にしたことのある、あの画像である。
気球を見続けてくださいね、と指示されると、画像の気球が勝手にピンボケになった後にピタリと焦点が合う。
この機械は眼球に赤外線を当てて屈折力を測定し視力を判定する仕組みらしいのだが、自己申告なしに度数を測れるので不思議な気分になる。
視力という自分にしかわからないはずの「見え方」というものを、気球が勝手に再現しているような気がするのだ。
『null-geist』収録の「撮れない」を読んだとき、ふと、そんなことを思い出した。
通っていた小学校の通学路にある、白くて古い家はモルタル外壁のヒビに沿って汚れが染み出ていて、傍らには雑草のハルジオンが生えていた。
今まですっかり忘れていた些細な通学路の景色だが、数年前に近所の白いモルタル壁の家の前を通りかかった際、壁のヒビとそこから滲む染み、傍で咲いているハルジオンを見つけでデジャヴに襲われ、通学路にあった家の記憶が唐突に蘇った。
二つの家はそっくりだった。
『para-ghost』収録の「黴女」を読んだとき、ふと、そんなことを思い出した。
『null-geist』および『para-ghost』は、自主制作の形で刊行された競作怪談/奇譚集である。
編著者の鈴木捧氏は昨年刊行の単著『エニグマをひらいて』に続き二度目の自主制作・出版となるが、今回は同時発売された二冊が対になっており、『null-geist』は蛙坂須美氏、ふうらい牡丹氏、『para-ghost』は高田公太氏、ひびきはじめ氏を迎えての、それぞれ趣の異なるトリニティ怪談集として仕上がっている。
null-geist=不在霊、para-ghost=偏在霊という題に相応しく、前者は幽霊の出てこない類の不条理怪談、後者は人々の生活の中に根付き、人間の意識という内側から発生する霊性やアニミズムを感じさせる話が多いという印象を受けた。
コンセプトも執筆陣の作家性も対照的ではあるが、鈴木氏の采配によってどちらも優劣なく魅力的な、それでいて鈴木氏の作家性と美意識ともいうべき怪談の佇まいが存分に味わえる。
折角なので、二冊とも取り上げたいと思う。
まず『null-geist』を紹介するにあたっては、ぜひ文藝2024年秋号に掲載された木澤佐登志氏による論考「この世界という怪異 実話怪談と思弁的怪異」も併せて目を通して頂きたいところ。
この論考では実話怪談における怪異を、「幽霊はそこに実在する」ことの証左、因果法則が適用される心霊としてではなく、私たちを取り巻く世界の側に属するもの——外部には私たちの理解をはるかに超えたものがあり、それが怪異として立ち現れるのではないか、という視点で実話怪談を読み解くものである。
この論考では蛙坂氏の作も取り上げられているのだが、なるほど『null-geist』は怪異のトリガーが私たちの外側にあり、場所性や歴史といった文脈が適用できない類の話が揃っている。
蛙坂須美氏は時に明快かつ鋭利に恐怖を描写し、キック力のある怪談を得意とするが、志向しているのは不条理であり、強烈な現象や登場人物以上に、解かれていない謎や開示されなかった情報等、怪異の余白部分が最も不気味である。
「かめをすてる」「かめをひろう」は解釈によっては妖怪の仕業のように思える描写もあるが、正体をそれとは断定できない展開を見せる話である。
「おれの知っている世界は、ほんとの世界とちゃうかった」という言葉は、本作の怪談の有り様を的確に言い表しているのではないだろうか。
いっぽう、ふうらい牡丹氏は不可思議で淡い怪談を得意とする印象があるが、存在しないはずの景色に迷い込んだような、記憶と事実に齟齬をきたす類の行き場のなさが通底している。
「赤い星空」や「家路」で埋めたハムスターなど、ボタンを掛け違えたような奇妙な記憶と空間の齟齬こそ、私たちの見えている世界が見せたエラーではないだろうか。
一見すると読み口は異なるが、外的な怪異に長けた作家二名と共に鈴木捧氏が競作したものとして、特筆すべきは#F6F7F8の章にある5編のUFO怪談がある(ここではざっくり未確認飛来物や物体、生物が登場する話をUFO怪談と言い切ってしまう)。
UFOはまさに外界から飛来する未知の存在であり、私たちが認識している世界の有り様、物理法則を凌駕する脅威である。
我々オカルト好きは、それらを観測、記録された証拠物——写真や動画といったメディアを通して消費し未知の存在に思いを馳せているが、本作の怪談5編には体験者が目撃した怪異としての未確認物と、それを記録したメディアが描写されている。
メディアは単に証拠物としてではなく、記録されたそれ自体も怪異の一部であるかのような印象を受け、またUFOとして体験者が認識したものが実は……というオチがつく怪談らしさもあり、UFO怪談というジャンルを今作で刷新させた感があり、非常に感銘を受けた。
ちなみに筆者のお気に入りは「撮れない」である。
体験者の視覚上の体験と、撮影した写真そのものに発生する物理的な現象の対比が面白く、得体の知れないものに侵食される気持ち悪さの質が斬新だ。
いっぽう、『para-ghost』は幽霊がきちんと登場するな、という印象がある。
高田公太氏は、怪談というひとときの体験を通して人間の悲喜こもごも、人生の有り様を描かんとする作家性が確立している作家であり、近作『青森の怖い話』では、青森という土地に生きる人々の方言交じりの言葉から滲み出る生活とその奥底にある死生観を掬い上げていた。
本作寄稿のやや長めの一編「女たちの顔」は、ひとりの男が人生で遭遇した女たち——妻や母だけでなく幽霊も含めた彼女らを、男の意識の中で数珠繋ぎにし、彼の冴えない暮らしと日常の鬱屈が、万華鏡のように少しずつ形を変えながら終わることなく迫ってくる。
ひびきはじめ氏もまた、人々の生活と日常、とりたてて語ることのない些細な日々の営みの中に生まれた怪談を掬い取る名手である。
『怪談琵琶湖一周』では琵琶湖周辺のご当地怪談を随筆を交えながら紹介し、外連味のないさらりと読みやすい文体で、砂金を見つけるように体験者の怪談から尊いものを見出す情緒の筆が冴えわたっていた。
今作でもその味わいは健在で、実体験を綴った「誰そ彼」は自身の体験による父視点と娘視点の素朴さが対比されている。
日常の些細な出来事としての怪談というものも、体験者にとっては唯一無二の体験であり、特に家族に纏わる怪談には恐怖だけではない価値や糧、時には人生の渡し船になり得る出来事もあることを思い出させてくれる。
鈴木捧氏はそれら人間の内面から染み出てきた怪談を束ねつつ、十八番である山の怪談や学校の怪談を織り交ぜて「偏在霊」というコンセプトを、情感や温度を殊更押し出すのではなく、ただそこにあるもの、として配置している。
それは一本の大木に成る木の葉とか、川べりの石ころとか、そういう類の連なりのように思える。
木の葉も石ころも、それ自体は変哲なく、ひとつひとつの違いがわからない。
どこにでもあるし、無数にある。今までもこれからも絶えることなくあり続ける。
そういった数えきれないものの中から一つの石や葉を拾って観察すると、筋や窪みの微細な特徴が一つ一つにあり、全く同一のものが存在しないことに思い至ると途方に暮れる。
偏在霊、というのも、きっとそういうことなのだろうと思う。