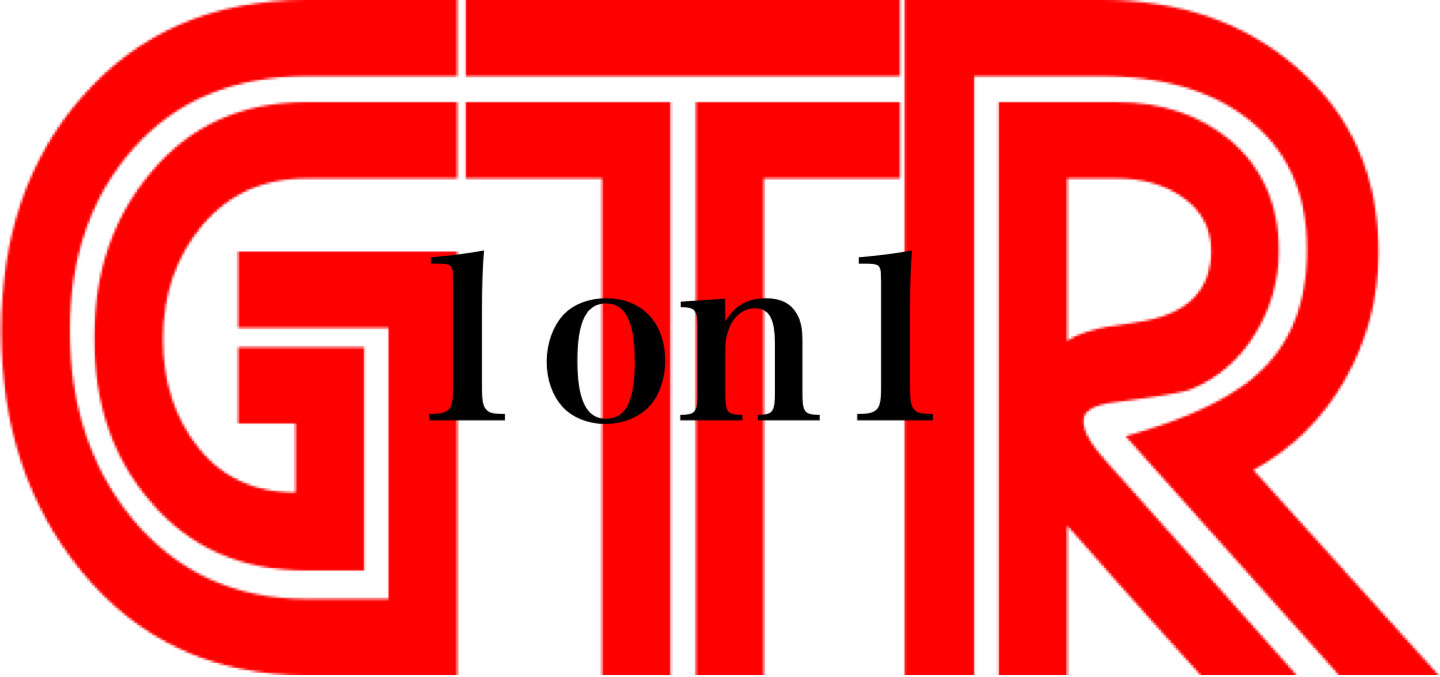昨年の11月に末期がんが原因で父を亡くした。
自営業でほとんど家にいなかった父だが、定休日の火曜日になるといつも昼間からビール片手にリビングで相撲やプロ野球観戦をしていた。夕方、学校が終わって玄関を開けて奥から漂ってくるのはカレーやシチューみたいなおいしそうな匂いではなく、決まって煙草の香りだった。
とはいえそれが特段嫌だったというわけではなく、その日が週に一度家族揃って食卓を囲む火曜日であると実感できて嬉しかった。
父は昭和に生きる頑固親父を地でいくような人間であり、いつもヨレた腹巻きを巻いて、阪神の選手が打って走れば手を叩き、凡打に倒れれば酷いヤジを飛ばす。
そのたびに「まぁたゲッツーや。ホンマこいつは何やらしてもあかんな。おまえと一緒や」と僕を指してへらへらと笑った。
使い古した腹巻きを巻いて半裸で歩き回るくせに、父は入れ歯を外した姿だけはなぜか絶対に家族に見せなかった。洗面所で入れ歯の洗浄をしているときは頑なに僕らが洗面所に入ることを嫌がった。そのたびに母は「お父さんアンタたちにカッコ悪いところ見せたくないのよ」と笑ったが、僕はまずはヨレた腹巻きから見直したらいいのにと思っていた。
元々大阪の老舗ホテルで寿司職人として勤めていた父は三十代で独立し、神戸の高級住宅地区の駅前に店を構えた。ホテル時代から懇意にしてくれていた常連客が独立後も店に通ってくれたため、父の店はそれなりに繁盛し、家族四人が慎ましく暮らしていく生活には事足りた。兄と二人、大学まで通わせてもらったことには感謝している。経営の心労はもちろんあっただろうが、少なくとも僕や兄の前では苦労の影を感じさせることはなかったように思う。
小学生のころ、父が突然「お前ら、旨い鮎を食わせてやる」と兄と僕を車に乗せ、二駅離れた自分の店まで向かったことがあった。ハイエースの助手席に中学生の兄が座ってその膝に僕が乗り、二人で鮎をどうやって食べるか盛り上がる中、息子たちにカッコいいところを見せたかったらしい父は深夜の国道でぐんぐんとスピードを上げ、走る車を追い抜いた。
必死になって「やめて! やめて!」と叫んでいると、突然ガァァン! という巨大なフライパンを擦り合わせたみたいな轟音と、激しい衝撃で車が大きく揺れた。車線変更の際に隣を走っていた大型トラックと接触したのだ。まるで曲芸みたいに片輪が浮いた車——。死んだと思った。走馬灯は店のいけすで元気に泳ぐ鮎の姿だった。しかし兄が咄嗟に運転席側へ体重をかけたことで車体はなんとか持ち直し、激しくバウンドしながら着地した。けたたましいクラクションとトラックから怒声が響く。痛いほど鳴る心臓を抑えながら、運転席の父を見ると、なぜか無表情で姿勢を正し、無言のままで真っすぐに前だけを見ていた。そのまま何もなかったかのように、またスピードを上げて変わり始めた信号を突っ切って、トラックが入れないような細い路地を曲がった。しばらく進んだ住宅街で車を停め、運転席を降りた父はPHSで母に電話をした。なにやらゴニョゴニョと話し込んでいたのだが、その横で兄がむちゃくちゃに激怒していたことを記憶している。当時父に謝られた記憶はないし、多分適当にごまかされたのだと思う。鮎を食べた記憶もない。この出来事のおかげで僕も兄も大人になるまで車に乗ることが酷いトラウマになった。
そんなクソッタレでむちゃくちゃな父は自身の健康にも気を遣うこともなかった。
昨年奥さんと息子を連れて店に顔を出した際、明らかに顔色が悪く痩せた父に異変を感じてすぐに病院へ連れていった。元々病院嫌いで検診なども受けたことのない父は、生まれて初めて受けた精密検査でステージ4の肺ガンであると発覚した。しかし今までの無軌道かつ自由奔放な生活を振り返ってみると、内心まぁそうだろうなと妙に納得できた。好きなだけ酒を飲んで煙草を吸い、阪神にヤジを飛ばしトラックに当て逃げた男なのだ。
それでも日に日にやせ衰えて死に近づく父を見ているとなんだか物悲しくもなった。父は医者に告げられた余命一年を待たずして早々に他界した。亡くなる前日、母と兄、僕と奥さんと息子の5人で見舞いに行ったとき、なぜか僕の手を握ったときではなく義理の娘である僕の奥さんの手を握り泣いていた父を見て、なんだかムカついたりもした。
翌朝、親父が危篤だと兄から連絡を受け、すぐに病院へ向かったが、昨日の面会で満足したのだろうか父は僕らの到着を待たずして早々に旅立っていった。
病室で泣きながら母が「お父さん、入れ歯いれよう。入れ歯大事やからね、入れ歯」と言いながら死んだ父の顎を持ち、硬直の始まった父の口に無理やり入れ歯を押し込む。「ホ」の形に口を開かされて死んだまま入れ歯を力任せにぐいぐい押し込むのが面白かった。「外れる! アゴ外れる!」と止めていると悲しい空気は吹き飛び、みんなで泣きながら笑った。
そこから一度自宅へ戻って準備を整えてからバタバタと斎場に移動した。斎場へ着いたとき、父の遺体はすでに病院から移動されていたのだが、父はなぜか黄金に輝くカプセルのような容器の中に寝かされていた。腐敗を防ぐため時折新鮮な空気が中に注入される最新型の保冷器? らしい。遺体の鮮度を保つことができるものだと聞いたが黄金である意味は分からないし、どこぞの国の王族かと思うぐらい無駄にぴかぴかと光っていた。その黄金のカプセルの中で紫色の唇と白い肌の父は寝かされていた。カプセル越しに父に向って「おとなしく寝とるやんけ」と言う僕に、兄が「死んどんねん」と笑っていた。
「フリーザみたい」と口に出そうになったが、昔、祖父の葬式の時に棺を覗き込んで「唇の色がフリーザ」と笑ったら兄に叱られたことを思い出したので黙っていた。
葬式の前、兄と二人で父の髭を整えた。本当なら専門の人に任せるらしいが、兄の申し出もあり二人でやることにした。二人とも「おくりびと」は視聴していたから問題はなかった。髭を剃り、鼻の毛を整えてから頭はギャッツビーでいい感じにした。父はいつも「悪魔くん」みたいに前髪だけを立てていたので、僕は「エロイムエッサイム~」とふざけながらも丁寧にいつもと同じようにしてやった。あとはのれんと割烹着も一緒に棺に入れた。
その晩、斎場の備え付けの風呂に入って伸び放題の髭を剃ろうとしたが、家に髭剃りを忘れてきたので仕方なく父の髭剃りを使った。父の匂いがする。ひどく懐かしかった。懐かしかったが、口の周りがジジイみたいな匂いになってしまい、オェとえずいた。すぐに顔を洗ったら匂いはすぐに消えた。
そこから僕以外は一度帰って僕だけが斎場に残り、父の棺の横でビールを飲みながら二人で最後の野球観戦をした。
その日、阪神タイガースは日本一になった。
葬式が終わりしばらくした頃、狼狽えたような興奮したような妙なテンションの母から連絡があった。
「お父さん死んでからね、不思議なことが起きるのよ」
「最初はねぇ、勘違いだと思ったんだけど……何度も落ちないでしょう?」
母が言うにはことが起こったのは父が亡くなって数日してからだそうだ。朝目覚めて洗面所に行くと決まってとあるものが流し台に落ちているのだ。
「——なにが落ちてんの?」
「ポリちゃん」
ポリちゃん? ポリちゃんってなんだ。
「なにそれ?」
「ポリちゃんよ。ほら、お父さんが使ってたやつ」
そのあとすぐ送られた写真には、流し台に落ちた入れ歯用のポリデントの箱が写っていた。
「何回も落ちるのよ。これは不思議よぉ」
そう話す母。
しかし、そもそもポリデントを「ポリちゃん」と呼ぶ母がひっかかる。
「いやわからんけども。そもそもポリデントのことポリちゃんって呼ぶの何なの」
「え、ポリちゃんはポリちゃんやないの」
「……そのポリちゃんが勝手に落ちたと」
「そうよ。それも何回もポリちゃんだけ。わたし絶対落ちないように確認してるのよ」
「りきゅう(実家の飼い猫)が落としてるんちゃうの」
「りきゅうじゃないよ。だって横で一緒に寝てるときに落ちるの。やっぱり『まだここにおるよぉ』って言ってるんかな、お父さん」
普段から不思議な話や怖い話を蒐集する中で、死んだ家族が何らかの方法をもってメッセージを送ってくる話も多くあるが、母の体験もそんな些細なエピソードの一つだろう。
もうすぐ父の一周忌になる。墓前に「ポリちゃん」を供えるのもいいかもしれない。