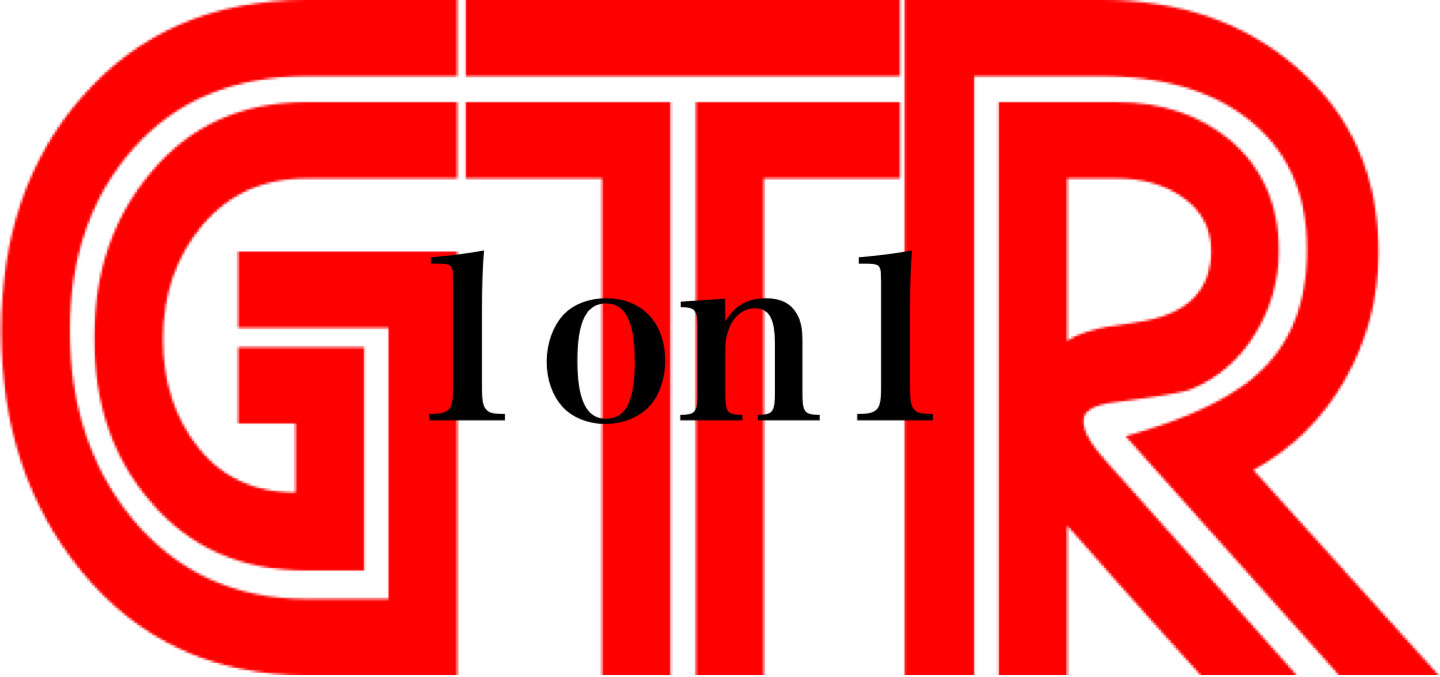十年以上前の話だ。
当時神戸の大学に通っていた僕は、仲の良かった男女数人の友人とともに県内で行われる大規模な花火大会に遊びに行くことになった。
僕は「なんでクソ暑い中わざわざ人ゴミに行かなきゃならんのだ」と文句を垂れていたが、出不精な僕に対し何かと気にかけてくれていた友人たちが誘ってくれたわけで、その好意を無駄にするのもどうかと思い参加したのだ。
開催場所となっていた河川敷へは電車を乗り継いで2時間弱はかかる。
現地での待ち合わせだったため、自宅を出たのは開始時刻のはるか前であり、その時点ですでに面倒にはなっていたのだがしぶしぶ駅に向かう。
新快速に乗り込むと、夕方ということもあり車内はまばらだった。
適当に席に座って窓の外を眺めながら一時間弱、いくつかの駅を経由しながら列車が目的の駅に近づく。
それにつれて車内には華やかな浴衣姿を着てはしゃぐ人の姿が目立つようになった。
外の景色も眺め飽きて座り続けたお尻が痛くなってきた頃にようやく目的の駅に着く。
人ごみに混じりながら電車から吐き出された僕が改札を抜けると、既に到着していた友人がこちらに手を振っているのを発見した。
大きな川向かいで打ち上がる花火を観るため僕たちは河川敷を目指した。
友人は皆華やかな浴衣や甚平を着ており、これから二ヶ月は続くだろう酷夏とすでに馴染む準備が整っているようにも見えた。
僕はといえば、半そで半パンの家着と変わらない恰好でボルヴィックをポケットに突っ込んでいた。
そこに財布とタバコとケータイも突っ込んでいたため、ズボンは不格好に膨れ上がっている。
きゃいきゃいとはしゃぐ友人たちを尻目に僕は一人一向に進まない大行列にうんざりとしていた。
広々とした河川敷に入ると、いくらか人ごみは緩和されそれぞれが好きな場所へ散って行く。
僕らも脇に並ぶ屋台を眺めながら花火が望める場所を求めて川上へ移動した。
「この辺りが一番見えるよ」
先導する友人は毎年参加しているらしく、絶好の観覧場所を案内してくれた。
斜面に腰を下ろして待っていると、既に真っ暗な河川敷に徐々に人が溢れていく気配がする。
帰り道のめんどくささを考えないように努めていると、ひゅるるるるる、と甲高い音を立てながら、小さな光が尾を引き空を垂直に登っていった。
その直後、光の粒が空に散って感嘆を上げる人々の横顔を照らす。
皆一様に顔を上げて音の鳴る瞬間に息をのむ。

いくつかの花火を見送っていると妙なことに気が付いた。
なんだか甘い煙の匂いがする。
妙に甘ったるい、安っぽい煙草のような香りが微かに鼻腔を刺激する。
僕の目の前に立っていたのはカップルらしき二人組。
浴衣を着た女性、その隣の男は黒いタンクトップ姿で、腕にはトライバルと呼ばれる刺青がびっしりと刻まれていた。
ヤンキーである。
顔を見なくても分かるほどのヤンキーが、すし詰め状態の河川敷で煙草を吸っている。
その副流煙が背後の僕の顔面に直撃している。
これだけ密集している場所で喫煙するなど非常識極まりないのだが、それにもかかわらず堂々と煙草をふかしている。
後ろからこのタンクトップヤンキーの首を掴み「おいケムたいんじゃボケ」と突っかかる選択肢もあるにはあるが、ときおり花火の光に照らされる丸太みたいな二本の腕を目にした瞬間、僕の怒りは不発花火みたくぷすんと萎んで消えた。
確かにこの河川敷のある地区はヤンキーが多く生息する土地である。
いうなれば、踏み入れてはいけない禁足地なのだ。
普段、間違って踏み入れてしまえば、身ぐるみを剥がされることも覚悟しなければならない。
もし踏み入れたなどと知られれば「お前、あそこへ行ったんか!」と普段は温厚な誰かの祖父や、どっかの祖母が血相を変えて怒鳴りつけるだろう。
そうして理由も話さず「日が昇るまで部屋から出るな」ときつく告げる。
深夜になると窓の外でヴォンヴォン! パパラパパラパラパラパラ~! と空ぶかしとクラクションが鳴り響き……。

という展開まで想像したとき、頭上でひと際大きな花火が上がる。
しかし、その花火はそれまでのものとは明らかに(少なくとも僕の目には)違って見えた。
距離が近い——。
はるか上空で煌びやかに散る花火は確かに美しい。
だが今の一発は一瞬、何が起こったのか理解できないほど、僕の目の前『超至近距離』で弾けていた。
周囲を見ても異変は無い。
みんなアホみたいに口を開けて夜空を見上げている。
そのときなぜか隣の友人が二重に見えた。
分身しているみたいに。
甚平姿の二重の友人をまじまじと見る。
その横の女を見ると、その女はなんだかナスビみたいに紫がかっていた。
なんだこれ? もう一度頭上で花火が打ち上がる。

——どぱぁおうぅん。
鼓膜に響いた破裂音はなぜか水中で聞いたみたいに酷くくぐもっていた。
耳に分厚い膜が張られたみたいだ。
顔を上げると花火がある。
花火があるが近い。
というか花火の中にいる。
きらきらと瞬く花火の中に自分がいるのだ。
またあの甘い匂いが鼻をつく。
思い切り吸い込んだ瞬間、謎の高揚感が体に満ちていく。

「ふぉぉぉおおお!!!」
謎の雄叫びを上げて僕は花火の中を泳いでいた。
高速で流れる流星群は僕を巻き込みながら物凄い速さで後ろに流れていく。
いったい何だこれは。
まさに奇跡体験である。

「花火すごぉい! 花火すごぉい!」
興奮し、友人の甚平の襟ぐりを掴む僕に「何?!何言ってんの?」と友人が戸惑っている。

「中ぁ!! 花火の中に入ってるぅ!」
気づけば僕はぴょんぴょんと南米辺りの部族みたく飛び跳ねていた。
花火の打ち上げは佳境に入っており、間髪入れずに打ち上がる。
その度に僕は花火の激しい煌めきに身を任せて「きゃほほほっっ! きゃほほほほっっ!」と南米にいるデカいサルみたいな不気味な歓声を上げていた。
友人たちは奇妙な生物を見るような困惑の視線を向けていたが、完全にゾーンに入った僕は誰にも止められない。
花火が打ち上がるたびに叫び散らした。
恐らく周囲の人々からすれば突如男が叫び出した挙句、マサイ族みたいに飛び跳ねるのだからさぞ恐怖したことだろう。
長く続いた花火大会は壮大なフィナーレを迎えて河川敷は元の暗がりに戻った。
僕もようやく落ち着きを取り戻しつつあったが、叫び散らしたことで完全に喉を潰していた。
そのしゃがれた声で「花火いぃ……花火ぃ……」と呟き続け、友人に「マジで大丈夫……? 何かヤバいクスリとかしてない……よね?」と心配されるに至った。
ヤンキーカップルは既にどこにも見えなくなっていて、はしゃぎ過ぎた僕はその場で盛大に嘔吐した。
夜の河川敷に初夏を告げるような心地よい風が吹き、僕の足元にはトシャったばかりのトウモロコシの粒が星屑みたいにキラキラと輝いていた。