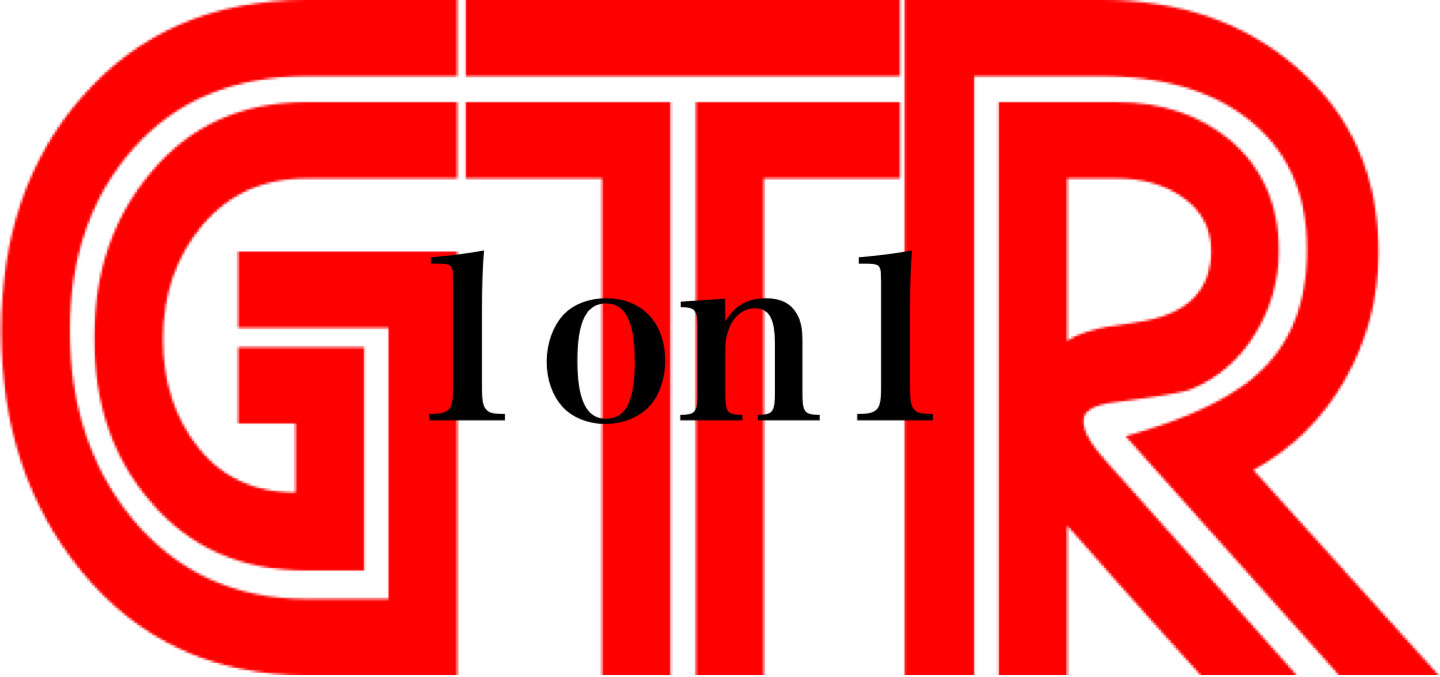昔、この地には愛し合う若い男女がいた。
二人は将来を誓い合ったが、身分の違いから両家親族から猛反対を受けてしまう。
ある夜、二人は村の高台にある大樹の下で、互いの体にガソリンをかけて心中を図った。
先に男が女の方に火をつけたが、激しく燃え上がる女の体と、耐え難い苦痛による女の断末魔に、男は怖気づいてしまった。
炎は大樹に燃え移り一層激しく燃え上がる。
心底恐ろしくなった男は、変わり果てた姿の女と、煌々と燃える大樹を残し、その場から逃げ去った。
その後すぐに男は逮捕され、牢獄に入れられた。
しかし、そこで男は毎晩何かに怯えるように叫び出し、看守に泣きつくようになる。
”助けてくれ。黒焦げの女が布団に入ってくる——”数日後、起床時間になっても起きない男を不審に思った看守が部屋を調べると、布団の中で男はすでに絶命していた。
【田舎の伝承の怖い話 怪談(山・海)】スレッドより抜粋
「——それで、その怪談を調べてるうちに、元を辿るとその地域に『妙な風習』があったことを知ったのです」
裕子は、自身が夢中になっているオカルト系動画配信者さながら、訳知り顔で語った。
「却下」
「ねぇホントお願い! 綾しか頼れないんだって」
人目を憚らず、裕子がTシャツの裾をつかんで懇願する。
「だいたいなんで私が、アンタの卒論手伝わなきゃいけないのよ。てか、Tシャツ伸びるからやめて」
裕子の手を振り払いながら綾が答える。
「だって綾、卒論ほとんど終わってるじゃん。それに私たちって親友じゃん。親友が困ってたら、助けるのがスジってもんじゃん」
「……アンタ、私のこと暇だと思ってるでしょ?」
「違うの?」
「はいもう絶対ヤダ。一人で頑張って」
「ウソウソウソ!」
大学からの帰り道、須藤綾は友人の裕子とそんなやり取りをしながら歩いていた。
綾が市内有数の繁華街に近い大学を選んで、一人暮らしを始めることにしたのは、地元から離れたい一心からだった。
ちょうど県境に位置するその地は、周囲を山に囲まれた山間部にある。
無駄に広いだけで、見渡す限り田んぼと山しかない。
一番近くのコンビニまでは、どれだけ自転車を飛ばしても30分。
そのコンビニも23時を回れば無常にもシャッターを閉めてしまう。
帰り道は陽が落ちると真っ暗で、自転車のライトを頼りにひたすら山道を走る必要があった。
ここでは不良や変質者に絡まれるより、猿や熊に出くわす可能性の方がはるかに高いのだ。
そんなドのつくほどの田舎から脱出するために、本来、部活や恋愛と忙しいはずの華の高校三年間を、都会の一人暮らしという目的遂行のために、ひたすら机に噛り付いて勉強に費やした。
そうして希望の大学に合格し、念願の一人暮らしを始めた——夢のキャンパスライフ。
田舎の芋っぽい女子高生を経て、見事に「都会の女子大生」という称号を手に入れた。
ただの女子大生ではない、頭に「都会の」と付くことがなにより重要なのだ。
グッバイ田舎——グッバイ猿と熊——。
大学生活をさらに彩るため、サークルにでも入ろうかと、入学してすぐいくつかの団体を見学しているとき、裕子とは出会った。
テニスサークル主催の新入生歓迎会の居酒屋で初めて会った裕子は、泥酔状態でトイレの便器を両手で抱えながら、ひたすらに唸っていた。
「大丈夫? これ飲みなよ」と適当に水を渡して席に戻ると、上級生男子が隅に集まってなにやらコソコソと話し込んでいた。
「お持ち帰り」などという言葉が聞こえ、下卑た笑い声が耳に入ったとたん、急速に酔いが醒めていった。
近くにいた別の上級生に五千円を渡し、相変わらず便器にすがり付いている裕子を担ぐようにして、タクシーに乗せて自宅まで連れ帰った。
翌朝、頭を抑えながら目覚めた裕子は「ココどこ!? あなた誰ですか!?」とひとしきり騒いだ後、トイレと間違えて駆け込んだ風呂場で盛大に吐いた。
少し落ち着いたころに、綾から改めて事情を聞かされた裕子は、ほとんどフローリングに頭が付くほどの謝罪を繰り返していた。
それ以来の仲である。
*
「はぁ……。裕子さぁ、アンタも知ってると思うけど。私、怖いの本当キライなの。そもそもその話だってネットのウワサでしょ?」
いくら親友の頼みであっても、ホラーやオカルトじみた話の調査なんて御免だ。
「大丈夫! 本当にお化けが出るわけでもないし!」
経済学を専攻している綾とは違い、彼女が所属しているのは地域観光学だった。
彼女の説明によれば『地域観光学』とは、特定の地域の歴史や問題にフォーカスし、地域別の問題の解決や発展について考える、ということが主題であるらしいが、詳しくはよく知らない。
その学びの集大成である卒業論文に、とある地域の『土着的信仰と近代史による地域集落への影響』をテーマにしたいのだという。
そう聞くと民俗学的分野であるようにも思える。
ホラーが大嫌いな綾には信じられないことだが、幼いころからオカルト話が大好きだった裕子は、大学では民俗学を学ぶつもりだったという。
しかし二人が通う大学には、民俗学の専攻がない。
そのため仕方なく、分野的に一番近しいと思われる『地域観光学』を選んだのだと聞いている。
裕子と知り合ってしばらくした頃「なんでこの大学を選んだの?」と聞くと「ここが一番家から近かったから」と彼女は答えた。
趣味も、大学を選んだ理由も、真逆の二人ではあったが、どういう理由かウマが合い、こうして一緒にいるというのは不思議なものだった。
当然のことながら、ハナから興味のない地域観光学の授業は裕子にとってひどく退屈なものでしかなかった。
彼女の興味は早々に失せ、おかげで単位も卒業可能な取得数ギリギリの状態で、卒業論文を完成させた生徒がちらほらと現れるこの時期になっても、テーマすらまだ決めかねていたのだった。
その中で、自分の興味がある分野と強引に結び付け、堂々と研究を進められるのだから、彼女なりにこのテーマに食い下がる理由があったのだ。
しかしオカルト好きなのは結構だが、なぜ私に助力を求めるのか。
当然、親友という立場である、という理由もあったが、それ以上に裕子がテーマとして掲げている地域というのが、まさに綾が生まれ育ってきた地元であるからに違いなかった。
「ねぇお願い! 力貸してよぉ」
泣き落としは裕子の常套手段だ。
「アンタが会いたいのは、うちのお祖母ちゃんでしょ?」
「それはそうだけど……他に知り合いなんていないもん」
表向きは地域の信仰文化と近代史についての調査だが、本当の目的はあの地域で昔信仰されていた、とある奇妙な風習と、先ほど聞かされた怪談話の実地取材だ。
そもそも裕子がこの卒業論文のテーマに辿り着いた理由も、つい先日、些細な会話の流れから「うちの地域では昔変な風習があったらしい」という綾の言葉に、裕子が目を輝かせながら「それ詳しく聞かせて!」としつこくせがんだからである。
そこから根掘り葉掘り聞き取り取材が始まったが,小さい頃に両親から軽く聞いただけで、ほとんど断片的にしか覚えていない。
そのあと独自に地域の歴史について調べ上げた裕子が、先ほど綾に向けて披露した、とあるネット上の怪談話に辿り着いたことが発端である。
「お祖母ちゃん最近はずっと寝たきりだし。それに八十過ぎてるからほとんど呆けてるよ。そもそもそんな変な風習が本当にあったのかも怪しいし」
「いいのいいの。なかったらテキトーに書いちゃうから!」
「あんたねぇ……」
いつものことだが、行き当たりばったりな裕子の性格にはほとほと呆れる。
「それにさ、話してるうちに他にも色々思い出したりするかもしれないじゃん」
無計画にもほどがあるだろう——考えなしに行動に移すのは、裕子の昔からの悪いクセだ。
「そんな上手くいかないと思うけど……」
「そこは腕の見せどころでしょ!」
一人勝手に盛り上がっている裕子が続ける。
「もうすぐ夏休みなんだしさ、パーッと遊びに行こうよ!もちろん調査はするけど、綾が育った地元を見てみたいっていうのは本当だし!」
こうなってしまうと何を言っても聞かないのは、これまでの付き合いで綾が一番よく分かっている。
「はぁ……。とりあえず、親に聞いてみるから」
「じゃあ決まりね!『親友が手土産いっぱい持っていきます』って伝えといて!」
「はいはい」
目を輝かせる裕子を横目に、綾は今日何度目かの大きな溜め息をついた。
*
「——本当に笑っちゃうくらいなんもないね。最高」
駅構内に一つしか無い古びた改札を抜けて、裕子がつぶやく。
大学が長い夏季休暇に入り、迎えた初めての週末。
二人は綾の地元である無人駅に降り立っていた。
「だから言ったじゃん」
綾がそう答えながら、トランクケースを引きずって構内を出る。
都会では見ない山に囲まれた田園風景がよほど珍しいのだろう。
道中から裕子は飽きもせず、携帯で写真を撮り続けていた。
駅を出た先の小さなロータリーに母の白い車が停まっているのが見えたので、右手を上げて大きく手を振る。
「——いつも綾がお世話になってます。綾の母です」
車のトランクを開け、荷物を詰めながら母が裕子に声を掛けた。
「とんでもないです! いつも綾ちゃんにはこっちがお世話になっていて——」
いつもより一つ高いトーンで話す二人に挟まれ、なんだか妙にくすぐったい。
話し込む二人をよそに綾は早々に車に乗り込み、後部座席に体を預けた。
*
「……綾の家って、もしかしてお金持ち?」
到着した自宅の門の前で、先ほどから裕子がぽかんと口を開けている。
「なわけないでしょ。お祖父ちゃんの代からの、大きいだけの古い家」
トランクからスーツケースを下ろしながら、綾が呆れたように告げた。
若くから鉄工所で働き、晩年は自身で立ち上げた会社を経営をしていた祖父は、その才覚と時代背景も手伝って、一代でそれなりの財を築いた。
家はその頃に建てられたものだ。
大きさだけはそれなりに見えるが、建てられてから一度も改装をしていないらしく、どこもかしこもガタがきている。
敷地内には母屋のほかに土壁でできた蔵があるが、今は雑多な物置き部屋として使われているだけだ。
夏の日差しから逃れるように玄関を入ると、実家特有のえもしれぬ懐かしい匂いが、微かに綾の鼻をくすぐった。
*
「この辺りで昔、変わった風習があったって聞いたんです。それを卒論のテーマにしたくて。それで、綾に連れてって欲しいってお願いしたんですよ」
「それで、こんな田舎まで来たわけだ」
先ほどから裕子は、綾の父にこの辺りの昔話や、祖母について熱心に聞き込んでいる。
「そうかそうか。まぁ、こんななんもない田舎だけど、ゆっくりしていくといいよ。もうすぐ祭りもあることだし」
「え! お祭りですか!? 行きたい行きたい!」
父の言葉に裕子が身を乗り出す。
「毎年やるんだよ。母さん! チラシ出してあげて」
父が呼びかけると、台所に立つ母が『○○地区夏祭り』と書かれていたチラシを持ってきて綾に手渡した。
チラシにはお祭りらしい提灯の絵と、浴衣姿で踊る男女のイラストが描かれている。
開催日時は十日後の土曜日。
「ねぇ、お祭りってどこでやるの?」
裕子が横からのぞき込む。
「ばあさんが入院してる『柏原(かしはら)総合病院』だよ。あそこの目の前がちょうど大きな広場になっててね、そこで毎年やるんだ。ほら、綾も小さいときに何度か連れてったこと、あっただろ?」
そう言って、父が新しい缶ビールに手を伸ばす。
柏原総合病院——。
チラシの右端にある協賛欄にも、一番大きく記されている。
確かに昔両親に連れられ、夏祭りに出かけた記憶はあった。
小学校の頃だろうか——あいにく途中から雨に降られてお気に入りの浴衣がびしょ濡れになってしまった苦い思い出しかない。
「私ってお祭り行ったら、わたがしと焼きトウモロコシはマストで食べるんだよね。楽しみだね」
チラシを奪った裕子が楽しそうな声を上げる。
「卒論どうすんのよ」
そういって裕子の手からチラシを取り上げる。
「それはもちろん、ちゃんとやりますよ。明日から!」
裕子は親指を立てて自信満々にこちらに向けた。
滞在期間は二週間。
梅雨が終わり、この地域にもいよいよ本格的な夏が到来する——。