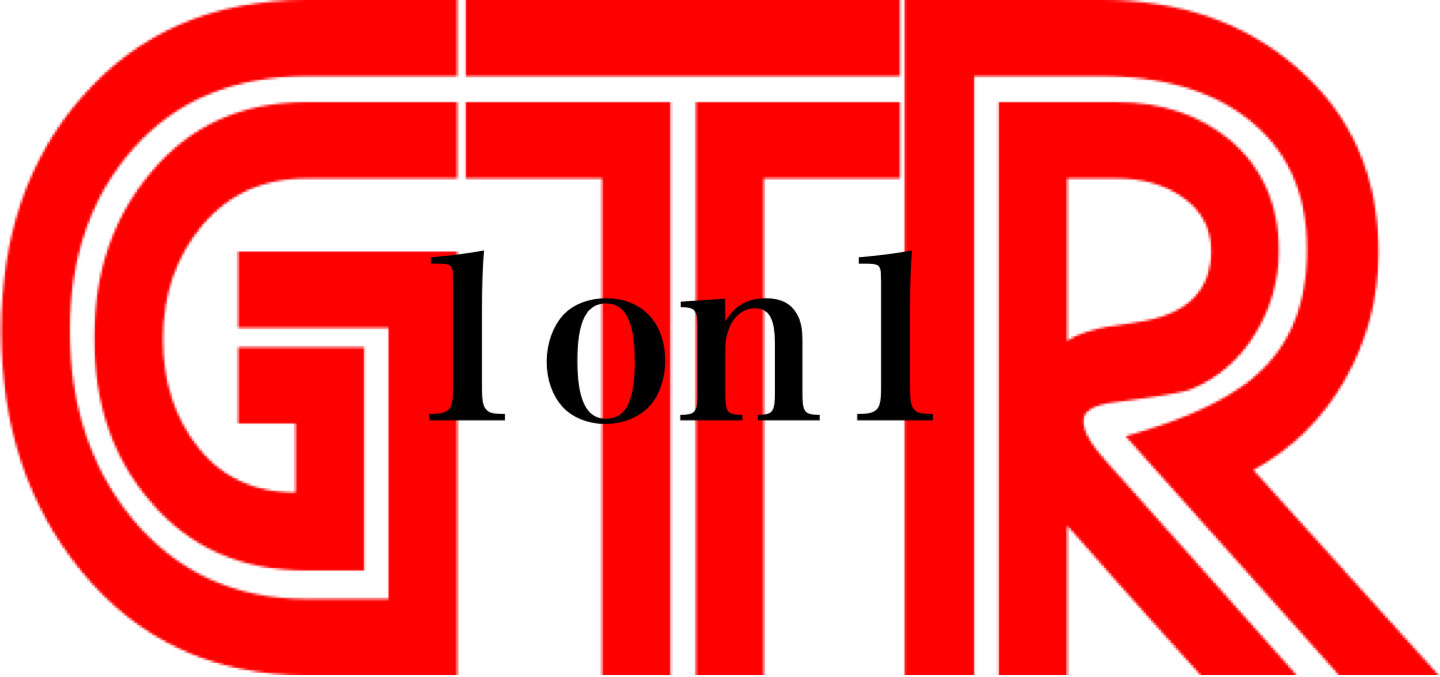壊れた雨垂れを伝い、いつの間にか屋内へ入り込んだ毒虫を見つけて、ナツは溜め息をついた。
まだ幼い弟が誤って噛まれぬよう、毒虫は見つけ次第叩き潰すか、箒で掃いて外へ追いやるのがナツの日課だった。
戸口を開けて空を見上げると、分厚い雲が小さなこの村に覆い被さって、地面を雨で濡らしている。
昼間だというのに薄暗く、聞こえてくるのは錆びたトタン屋根を弾く耳障りな雨音だけで、それが酷くナツの気分を沈ませた。
この時期はいつもこうだ。
夏になると嫌と云うほど日照りが続くくせに、この時期だけは鬱陶しいほど雨が延々と降り続く。
雨は田畑を潤すが、こうも毎日だと野菜は腐って売り物にならなくなる。
足元でのたくっている毒虫を、汚れた草履の底で踏み潰し顔を上げると、近くのドブ川の嫌な匂いが鼻をついた。
母は雨の中にもかかわらず、飽きもせずいつもの場所へ出かけていた。このところ母は一人で「あれ」の元へ通っている。
「お父ちゃんのことやけ、好きにやらせぇ」
姉はそう言うが、戦争が終わって二年も経つというのに、帰らない父の生存を未だ信じているのは母だけだ。
戦争で死ぬと、国から「シボウコウホウ」というものが家族の元へ届けられると聞いたことがある。シボウコウホウ——。言葉の意味は分からないが、ナツにとってそれは不吉な響きを持つ、忌むべきものだった。
しかしそれが届かない以上、母は父の生還を信じて待ち続けるしかないのだろう。すっぱりと父を諦めて生きられるほど、母は強かな人ではない。
そのことは幼いナツにも分かっている。縋る先が神であれなんであれ、母の好きにさせてやろうというのが、姉妹二人の決め事だった。
*
姉はあまり行きたがらないが、ナツはよく母と二人で裏山に登り、「それ」の元へ出向いた。その道中だけは母と二人きりになれるからだ。普段は姉や弟と平等に分け合う母の優しさを、このときだけは独り占めにできた。
母が「それ」に向かって手を合わせている間、ナツも隣でしゃがみ、手を合わせながら、うっすらと目を開けては母を盗み見る。
「ナツはお母ちゃんに似て美人やけぇ、貰い手には困らんのう」
姉の言う通り、母の横顔は自分とよく似ているように思う。綺麗に通った鼻筋なんかは特にそうだ。ナツは自分の鼻筋にそっと触れるたび、母との確かな繋がりを感じるようで嬉しくなった。
いつかの裏山からの帰り道、夕陽に染まる山道を下りながら、母が後ろを着いて歩くナツに告げたことを思い出す。
この村で生きて、死ぬ女はみんな神様になる。
入れ替わって役割を回すんよ。
叶える側に回るんよ。
やけえ、生きてるうちにたくさん神様にお願い事しなさいよ——。
その意味をよく理解できぬまま、曖昧に頷いたナツを見つめ、母が優しく頭を撫でる。
母の細い指の感触を、ナツは今でもはっきりと覚えている。
暑さがようやく収まり始めた、ある晩夏のことだった。
*
翌年の夏も、ナツは母と裏山にいた。
六月に降り続いた雨は一切降らなくなり、日が経つうちに田畑はみるみる干上がっていった。昨年からの備蓄などとうに食べ尽くしており、ただでさえ貧しかった日々の生活は、一層の困窮を極めた。
姉と弟を家に残し、ナツと母の二人で裏山へ登っては、懸命に手を合わせて祈る。
「——さん」
そのとき、確かに母の口から漏れ出たのは、未だ戦地から帰らない父の名だった。
山を下って家へ戻ると、戸口の前に呆然と立ち尽くす姉の姿があった。姉の腕には、まだぬくもりの残る痩せた弟の亡骸が抱かれていた。
幼い弟は、一度たりとも腹を満たすことがないまま、その短い生涯を静かに終えた。
弟の名を繰り返し叫ぶ母の悲痛な声だけが、雲一つない晴天に空しく響いていた。
*
弟が死んで数年した頃。
相変わらず生活は苦しかったが、そんな中でもナツの心を躍らせる出来事が起こった。姉の縁談が決まったのだ。
相手は隣の集落出身の青年で、今は一つ山を越えた先の町で、小さな鉄工所に勤めているらしい。
ナツは自分のことのように喜んだが、姉が家を離れる日が近づくにつれて、激しい寂しさに胸を締め付けられた。幸せそうに笑う姉を心の底から
祝福したい。けれど、生まれてからのあいだ絶えずそばにいた、わが身同然の姉と離れて暮らすなど、想像もできない。泣いて姉に縋り付き、引き留めたい衝動に何度も駆られたが、そのたびに姉の幸せを邪魔してはいけない、笑顔で見送るのだ、と自分に言い聞かせて思いとどまった。
姉が嫁ぐその日も、ナツは一人早朝に家を抜け出して裏山を登り、「それ」の前で手を合わせ姉の幸せを祈っていた。
どうかこれ以上、姉が辛い思いをせずに暮らせますように。どうか姉がこの先、幸せに過ごせますように——。
*
姉のいない母と二人きりの生活は寂しいものだったが、それでもナツは懸命に生きた。母と二人、毎日のように裏山へ通い、姉の幸せと日々の平穏を祈った。
ここには幼くして死んだ弟の魂もある。弟もきっと神様の元で、自分たちを見守ってくれている。そう考えると侘びしい生活にも耐えられた。
姉の幸せを願いながら、母と二人慎ましく暮らせていけるのであれば、それだけでナツは満足だった。
*
いくつかの季節を超えた頃、国からの供給命令が緩和され、いくらか手元に残るようになった野菜を売りに出すために、ナツは一人で町の市場を訪れるようになっていた。そこでナツは思いもよらぬ出会いを果たすことになる。
「一つ、貰おか」
ナツが顔を上げると、精悍な顔つきの背の高い青年が目の前に立っている。姉と同じくらいの歳だろうか。青年が続けてナツに話しかける。
「この辺じゃ見よらん顔やけども、名前を聞いてもええか?」
「はぁ、『ナツ』と言います……」
「——ナツ。ええ名前じゃのう。夏は好きじゃ」
「はぁ、はい……」
季節のことだと理解はしていたが、小さな村から出たことのないナツが男から「好きだ」などと言われた経験があるはずもなく、それが自分に対してではないと分かってはいても、顔が熱くなるのを感じた。カッと頬が熱くなり、咄嗟に顔を伏せる。青年はそんなナツを見て、
「いやぁ、すまんすまん。からかっとる訳ではないぞ」
と、からから笑った。
青年は「祥吉」と名乗った。祥吉とは、それからしばしば市場で顔を合わせるようになったが、村で見ない清潔な身なりと、快活に笑う祥吉に、ナツは急速に惹かれていった。二人が恋仲になるにはそう長い時間かからなかった。そうしていつしかナツは、昭吉との結婚を夢見るようになっていった。
これまでの人生を振り返ってみても、ナツには幸せと呼べる思い出がほとんどなかった。貧しい生活の中で、ただ必死になって生きてきたのだ。
そんな自分が、この先この人と生きていくことができるのならば、どれほどまでに満たされるだろうか——。
いつものように、裏山へ足を運び「それ」に向かって手を合わせる。
もし、許されるのなら、せめてこの幸せができるだけ長く続きますように。どうかあの人と添い遂げられますように——。
このとき初めて、ナツは自分の幸せのためだけに祈った。
しかし、祥吉の親族、特に祖父母は二人の関係をよく思わなかった。祥吉の家は戦前から代々と続く名家である。ひとたび祥吉とナツの関係を知ると、あらゆる手段で二人の仲を裂こうとした。
執拗な嫌がらせを受けても、ナツと祥吉は頑なに離れなかった。ナツは祥吉の腕の中で、この幸せだけは手放すまいと人知れず強く胸に決めていた。
しかし、二人の態度に業を煮やした祥吉の祖父は、祥吉の縁談を強引に進めた。そのことで大きく事態が変わった。縁談相手はその地区一番の有力者の娘である。この縁談が今後の一族全体へどれだけ大きな影響を及ぼすのかは、祥吉やナツにも理解できた。
若い二人に、もはや選択肢は残されてはいなかった。
*
人気のない深夜の山道を、祥吉の手を取って歩く。さんざん歩き慣れたこの道も、祥吉と歩くのはひどく新鮮で、不思議な気持ちになった。
村の裏山にある「それ」の存在を、いつか祥吉に話したことがある。最初は子どもだましの馬鹿げた話だと笑っていた祥吉だったが、ナツの真剣な目を見て「笑って悪かった」とすぐに謝罪をした。いつか二人で挨拶に行こうと約束してくれたのは、まだ寒さの残る春先だっただろうか——。
思い返せば、この場所にはたくさんの思い出がある。これまでの人生で、ナツが何度も通い詰めた場所だ。
母の横顔や、細い指。姉の幸せ。弟の魂。ナツの生涯の全てがここにあった。
私は確かに神と生きたのだ。
幼いころから見続けてきた姿と変わることなく、大樹はそこにあった。
大樹の根元に二人で腰を下ろす。
祥吉が何も言わず、静かにナツの肩を抱いた。
これから成し遂げようとしている行いに、不思議と恐怖はない。代わりにあるのは、愛する男の腕に抱かれた温もりと、この身を焦がす至上の愛だった。
ここで一つになれるなら、それもいい。
ナツの頬を伝う涙だけが、その身の不幸を証明していた。
——泣くな、美人が台無しじゃ。
ナツは腕の中で、郷里を離れる姉が最後にかけてくれた言葉を思い出していた。
優しい姉のことだ。弟を亡くしたうえに、妹までいなくなったと知ったら、きっと自分のことのように泣くのだろう。
思いを綴ったたくさんの手紙も、幸せに過ごしている姉を悲しませまいと、結局一通も出すことはなかった。
姉はいつか忘れるのだろうか。
ならば私はこの場所で、彼女の幸せを静かに祈ろう。
この村で生きて死ぬ女は皆、神様になる——。
あの日の母の声が蘇る。
私は愛しいこの人と、腹に宿ったばかりのこの幼い魂と、ここで交わり、神になる。
頭上の葉が一斉に揺れ、数羽の黒い影がけたたましい鳴き声を上げて飛び去っていく。
今、確かにナツの願いは聞き届けられた。
それがどれほど残酷な願いだったとしても。
神様——。
祥吉と目が合う。
どちらともなく微笑み、二人は深く息を吐く。
そして互いの喉に当てた鋭い刃に、あらん限りの力を込めた。