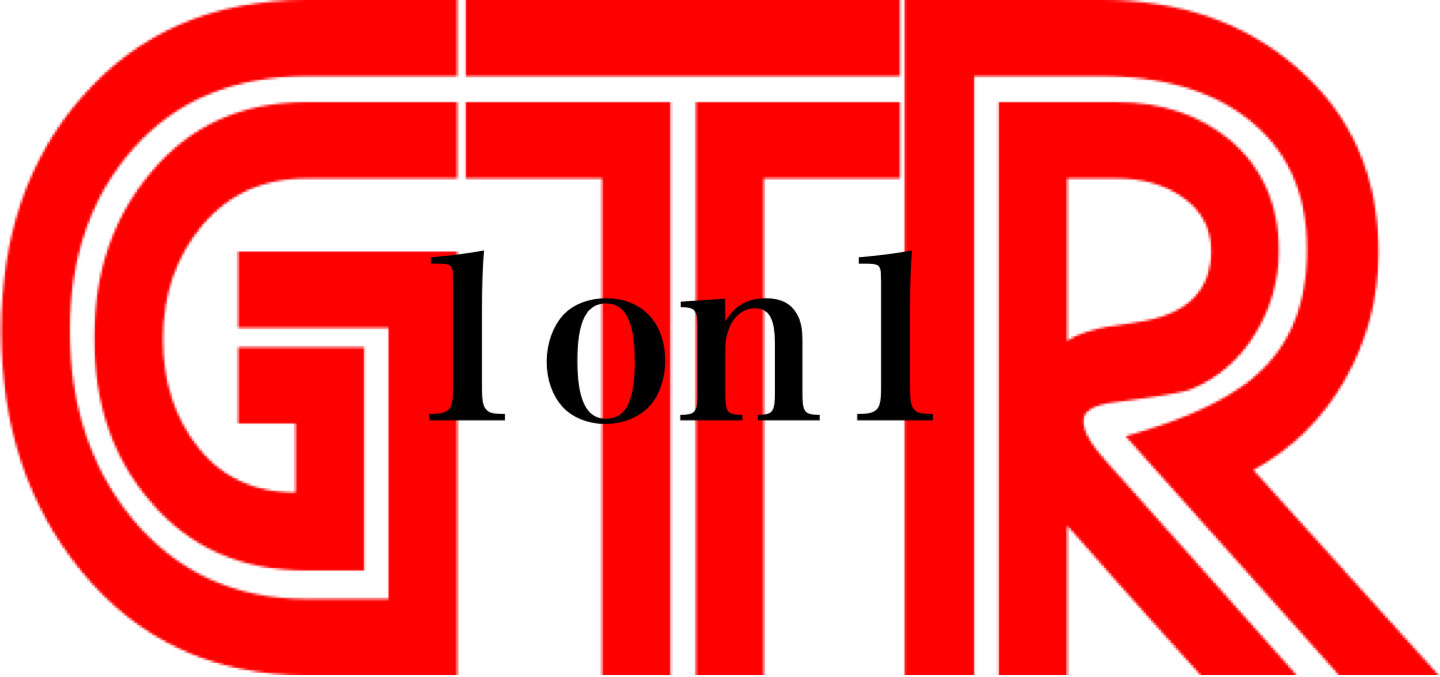わたしは、どういうつもりか妙にしなやかに身体をよじらせたり、かと思えば思い出したように首をぐりぐり動かして会場の様子を眺めたりするにゃんころみーこを無視して、目の前のテーブルに並べていた自著を手早く片付けた。来場者のほとんどがわたしの号令に素直に従ってくれているようで、会計の列が少なくなると共に、会場はみるみる静かになっていったものの、にゃんころみーこだけはずっと変わらぬ様相だったのだ。それは「このままチンポッコに泊まるつもりですか?」と皮肉のひとつでも言ってやりたくなるほどだった。
「高田先生、今日、打ち上げやる感じでした?」
両手に差し入れの紙袋をいくつもぶらさげた助麻呂が、カウンターの椅子で休んでいるわたしにそう言った。
「ああ。助麻呂さんが時間あるならこのままここで軽く乾杯しようと思ってたけど」
「軽くですね。軽くならぼくも時間ありますよ。実は締め切りが重なってて、時間があまりないんですけど。ええ」
どういうつもりか助麻呂はいつもわたしにこうやって自分がいかに執筆依頼をたくさんもらっているのかを教えてくるのである。彼に悪気があるのかどうか分からないが、悪気がないからと万年仕事なしのわたしにこのような情報を教えるべきではないはずなのだ。こういう無自覚に人を傷つける輩はほとんど病気である。そして、この病気の度合いが強い人から順に売れていくのが怪談界というものなのだ。
「……軽くなら」
助麻呂の背後からそう声がし、見るといつの間にかにゃんころみーこが立っていた。
「え?」
わたしは彼女の意図が掴めず、聞き返した。
「軽くならあたしも……」
そのとき、助麻呂は真顔ともおどけているとも知れぬ中庸の顔つきをしてにゃんころみーこを見ていた。助麻呂は面倒ごとを避けるのに長けている。おそらくは成り行きをわたしに任せるつもりなのであろう。
「いえ。申し訳ないですが、演者と関係者のみの打ち上げでして」
「……あっそ」恐ろしくつっけんどんな響きがそこにはあった。
「……すみません、今日はありが……あ……」
にゃんころみーこは、団体行動を思わせる動きで回れ右をし、さっと会場から出ていった。
「なんだ、高田先生。あのお客さん、打ち上げに入れてもよかったのに」
この助麻呂のブラックジョークのおかげでわたしの緊張は和らいだ。
「あのお客さん、知ってる?」
「知ってますよ。ちつさんのストーカーでしょ? にゃんころみーこ」
「え。そうなの? 木爪乃ちつの追っかけ? それは初めて聞いた」
「追っかけなんてものじゃないですよ。ストーカーですよ。自宅の前に立ってたことあるって、本人から聞きましたよ」
若手人気怪談師の木爪乃ちつはファンサービスが過剰なほど旺盛で、それは業界から「いつまでもファンの相手をしているから打ち上げもできないし、あのムーブのせいで会場から出て行かないファンの扱いに困っている」と評されるほどだった。ここ最近、SNSで適応障害なのか鬱なのかはっきり言わなかったものの、「メンタルを壊している」と発表したのが記憶に新しい。とはいえ、わたしには「自分でファンを強火にかけておきながら、いざ燃え上がったファンの対応に疲弊とはこれいかに」という具合にしか見えず、ちつは馬鹿か間抜けなのだろうと看做すばかりである。器が小さい輩がリスクヘッジも考えず、人気ユーチューバー気取りで舞い上がるからこんなことになるのだ。売れる心の量が少ないなら、はなからあまり心を売らなければいいだけだ。
「ちつさん、にゃんころみーこと寝ちゃったみたいですね。残念な話、ストーカー化させたのは彼ですよ。マンドラゴラに水をやる奴の気が知れないですよね。うふふふふ」
「えっ!」
人気怪談師とはいえその実パッとしない風貌のおじさんと、さきほど見たにゃんころみーこがねっとりと絡み合う様子が脳裏に浮かぶと、むしろこちらの鬱の気がむくむくと膨れ上がる。わたしは登場人物の誰もが可哀想に思えた。
「いっひっひっひっひ。ちつくんもやりますよねえ。いっひっひっひっひ」
助麻呂はSNS上ではいかにも怪談にしか興味ありません、わたしは怪談にひたむきですといった仕草を取っているが、実際はこのようなゴシップ大好きおじさんなのでしょうもない。
助麻呂が会場を去ったのち、わたしはチンポッコの店長としばらく談笑した。今回のイベントは小便をたらふく飲む映像がBAN対象になるのが明らかだったので配信は見合わせていたものの、助麻呂の人気で満席となったのでそれなりのギャラにはなりそうだ。
雑居ビルの二階に位置するチンポッコから階段を降り、通りに出た。
商店街の明かりはまばらだった。わたしは駅方面に顔を向けた。
「あっ……」
わたしは三十メートルほど先の電柱の横に立つにゃんころみーこを認め、思わず声を漏らした。
踵を返すべきかどうか悩む暇もなかった。
「高田センセ! お疲れ様です!」
胃から小便が込み上げ、重いゲップが出た。
視界が少し黄色く滲む。
にゃんころみーこは、まるで壊れた人形のゼンマイ仕掛けのようなぎこちなさで、身体を揺らしながら近づいてきた。その目は商店街の薄暗い街灯に照らされて妙にぎらついていた。わたしの足は地面に縫い付けられたように動かなかった。
「高田センセ、ちょっと、いいですか?」
彼女の声は、さっきのつっけんどんな調子とは打って変わって、妙に甘ったるい。まるで、ちつに絡みつくときの口調を真似しているかのようだった。胃の底から再び小便の味が込み上げ、わたしは思わず唾を飲み込んだ。
「いや、ちょっと急いでて……電車、逃しちゃうんで」
適当な言い訳を口にしながら、わたしは一歩後ずさった。しかし、にゃんころみーこはわたしの動きに合わせて一歩踏み出し、距離を詰める。彼女の手に握られたコンビニのビニール袋が、風もないのにカサカサと鳴っていた。
「センセ、ちつさんのこと、どう思います?」
突然の質問だった。わたしは助麻呂との会話を彼女がどこかで聞いていたのではないかと疑い、怯えた。にゃんころみーこの目は、まるでわたしの脳みそを直接覗き込むかのように、じっとわたしを捉えている。彼女の口元に笑みとも嘲りともつかぬ歪んだ線が浮かぶ。
「どうって……まあ、頑張ってるんじゃない? 人気者だしね……」
当たり障りのない答えを返しながら、わたしは視線を逸らし、この場からどう逃げようかと考えた。するとにゃんころみーこはさらに一歩近づき、まるでわたしの逃げ道を塞ぐように身体を傾けた。「頑張ってる、かぁ。ふふ、センセってほんと真面目ですよね。でもさ、ちつさん、最近変なんですよ。知ってます?」
彼女の声が急に低くなり、まるで耳元で囁くような響きになった。にゃんころみーこがちつのストーカーだと、助麻呂は言っていた。だが、この女の雰囲気は、ただの熱狂的なファンとは違う。何か、もっと深い、得体の知れないものを感じる。
「変って……何?」
聞くべきじゃなかった。頭のどこかでそう叫ぶ声がしたが、口は勝手に動いていた。にゃんころみーこは、まるでその瞬間を待っていたかのように、くすくすと笑い始めた。彼女の笑い声は、まるで空き缶が転がるような、乾いた音だった。
「センセ、ちつさん、最近、鏡見てないみたいなんですよ。自分の顔、ちゃんと見てない。だって、鏡に映るの、ちつさんじゃないもん」
一瞬、時間が止まったような気がした。
不景気な商店街が、にゃんころみーこの顔を不気味な影で切り取る。
彼女の目は、まるで底のない井戸のように暗く、わたしを吸い込むようにじっと見つめている。
「は……何? 何だって?」
声が震えるのを抑えきれなかった。にゃんころみーこは、ゆっくりとビニール袋を掲げ、中から何かを取り出した。それは、掌に収まるくらいの小さな手鏡だった。表面は古びて曇り、枠には奇妙な模様が刻まれている。彼女はそれをわたしに差し出し、まるで子猫をあやすような声で言った。
「センセ、ちょっと見てみてください。ね? ほら、怖くないですよ」
わたしは反射的に後ずさったが、背後には電柱があって、もう逃げ場はない。にゃんころみーこは手鏡をさらに近づけ、わたしに突きつける。鏡の表面に、わたしの顔が映る、はずだった。
だが、それはわたしの顔ではなかった。
そこに映っていたのは、木爪乃ちつの顔だった。それはわたしの知るちつとも違う、あの行き過ぎたファンサービスの裏にある、疲れ果てて歪んだちつの顔だった。鏡の中のちつはわたしを睨みつけていた。わたしは悲鳴を上げそうになり、慌てて目を逸らした。
「な……何! 何だこれ!」
にゃんころみーこは、まるでわたしの反応を楽しむように、くすくすと笑い続けた。彼女の手鏡を握る指は、まるで骨だけになったかのように白く、異様に細い。
「センセ、ちつさん、ファンを燃やしすぎたんですよ。燃えたファンは、ちつさんの心を食べて、鏡に閉じ込めたんです。あたし、ちつさんのファンだったから、知ってるんです。だって、あたしも燃えた一人だから」
彼女の声は、まるで風に揺れるすすきのようになめらかで、ぞっとするほど冷たかった。わたしはにゃんころみーこがただのストーカーではないことを悟った。この女は、ちつの心を喰らい、鏡に閉じ込めた何かの化身だ。怪談作家として、数々の話を聞いてきたわたしだが、これは本物だ。肌が粟立ち、心臓が喉から飛び出しそうになる。
「センセ、怪談師ですよね? なら、教えてください。この鏡、どうすればいい? ちつさん、助けてって言ってるんですよ。ほら、聞こえるでしょ?」
にゃんころみーこが手鏡を耳元に近づけると、かすかな囁き声が聞こえてきた。それは、ちつの声だった。「助けて……高田さん……助けて……」と、途切れ途切れに繰り返している。わたしは恐怖で足が震え、膝から崩れそうになった。
そのとき、にゃんころみーこが突然、手鏡を地面に叩きつけた。ガシャンという音と共に、鏡は粉々に砕け散り、破片が商店街の地面に散らばる。破片の一つ一つに、ちつの顔が映っている。いや、ちつだけではない。助麻呂の顔、わたしの顔、そして知らない無数の顔が、破片の中で蠢いている。
「センセ、逃げないでくださいね。だって、センセも怪談師でしょ? 怪談師は、こういう話を、ちゃんと終わらせなきゃ」
「わ、わたしは怪談師ではない! 怪談作家だ! 表現者なんだ!」
自分が何をアピールしているのか、自分でも分からなかった。とにかく、これが夢なら今すぐ覚めてくれとわたしは願った。
にゃんころみーこは、破片を拾い上げ、わたしに投げつけてきた。破片がわたしの腕に突き刺さり、鋭い痛みが走る。血が流れ、視界が再び小便世界となる。彼女の笑い声が、商店街全体に響き渡った。わたしは逃げようとする。だが、足元に散らばる破片がまるで生き物のように這い上がり、わたしの身体に絡みついてくる。
「もう! もう勘弁してくれ!」
そこで目が覚めた。
思い切り半身を上げると、目の前に見慣れぬ大画面のテレビ、スロット台、大きなソファなどが目に入った。
ダブルベッドに横たわるわたしの隣では裸のにゃんころみーこが口を開けて眠っていた。
彼女の口内は虫歯だらけで、わたしは「デカダンス」とひとりごちた。
(続く)

高田公太
青森県弘前市在住の作家、詩人、エッセイスト。
近作は「絶怪」(竹書房刊)の編著。
note→高田公太のnote
YouTube→オカさん
HP→高田公太 Official Home Page