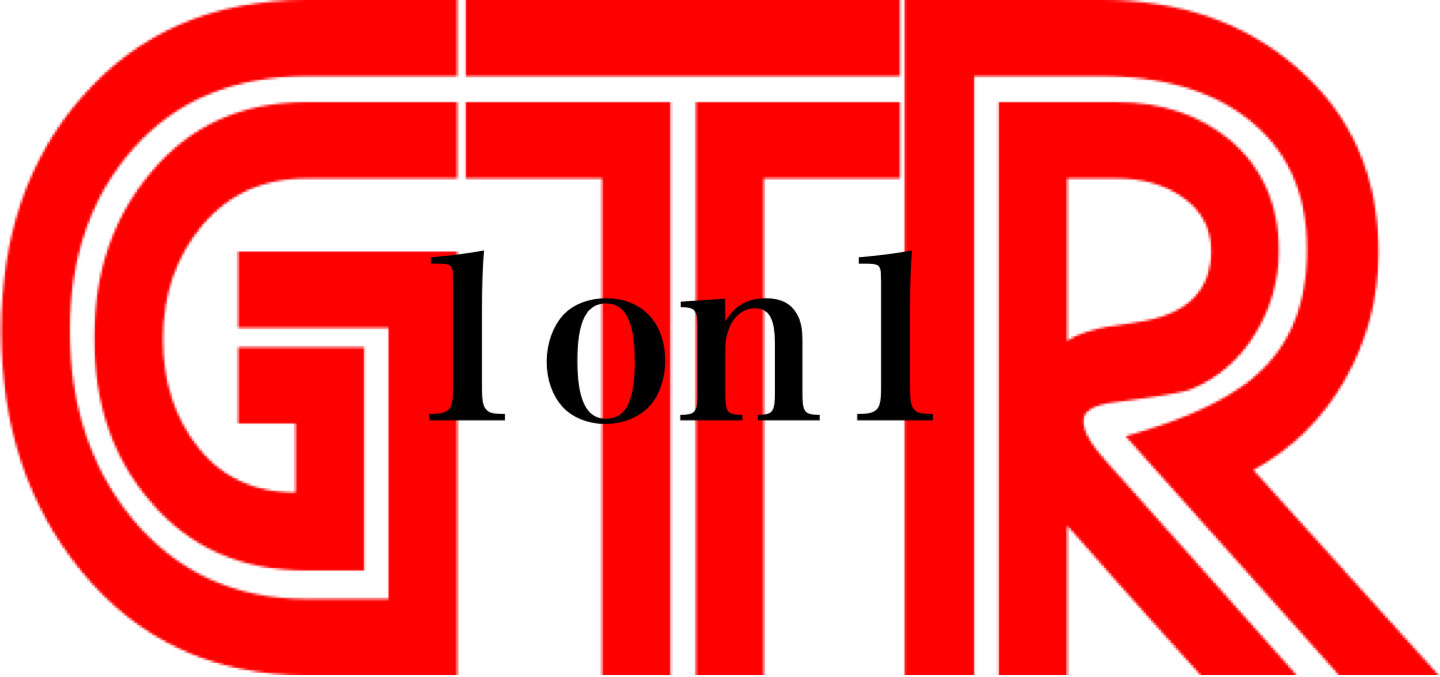なぜ自分が現在「怪談作家」として活動できているのかを省みてみたところ、ひとえに己がとんでもなく堕落しきった愚か者であることに起因しているのだろうと思い至った。修練、修行に該当する行為が嫌いで、若いころはミュージシャンになりたいという夢はあったものの、まったく努力しなかった。作家デビューのきっかけとなった実話怪談の大会の公募に投稿した理由は、投稿要項も投稿方法も馬鹿みたいに簡単だったからで、もし面倒なそれだったならば投稿はしていない。その上、実話怪談は他人から聞いた話を思うように書けばいいだけなので、とても楽だ。楽のオンパレードに乗っかっただけに過ぎないのである。そうして目ざとく自堕落な道を歩もうとし、今に至る。気楽にやってたら簡単にデビューできたわけだ。本を出すと周囲からちやほやされ、とても気持ち良かったものだ。だらだらと生きつつも「何かになりたい」とだけは思っていたので、作家という肩書きを持てたのが嬉しかった。しかし、そんな心地よさは数年もしたら消えた。知らぬ間に小さな世間から作家が作家の仕事をするのは当たり前と見做されるようになったため、まったくちやほやされなくなったのである。ちやほやの熱が冷めてから周りを見れば、ミステリ、純文学、SFなどわたしが好むジャンルで歳下の作家が華々しくデビューを果たし、何十万部と本を売って稼いでいる。かたや自分は、一万から五千人ほどのマニアや「なんとなく怖そうだから買ってみた」というファン未満の人々に向けて書いているだけで、世間に知られるような名前になっていない。結局わたしは誰もが一か月もしたら忘れるような仕事をひたすら続けているだけの自称作家でしかないのだ。何かになれた、というのは勘違いで、ずっと何にもなれていないまま、ぬるま湯に漬かっていただけなのだ。しかし、それに気がついていても別段何を努力するわけでもなく、ただルサンチマンと承認欲求の炎に身体を焼かれて生きている。
コロナ禍を経てオカルトYouTubeチャンネルが流行りだすと、いよいよ怪談作家という肩書きが持つ最後のきらめきは消えた。いや、いくらか売れている作家もいるので、自分がきらめきと思っていたものの搾りかすが絶えたというべきか。誰もが流行りのオカルト系のYouTuberをもてはやし、「これぞ怪談だ」と、まるで古くから活動するわたしなぞはなからこの世にいないかのように浮かれていた。YouTuberは平気で「わたしは本を読みませんから」と言い、長年活動している怪談作家に対してリスペクトを表明している場面はほとんどなかった。なぜなら、そんなことをしてもバズらないからであり、彼らにとってもわたしの存在は無も同然であるからだ。わたしは何度も「おい! おれは先輩だぞ! おれを立てろ! おれはここにいる!」と叫びたくなったし、「お前らは全然面白くないのに、なんで売れるんだ! バカな客ばかりだ!」と呪いたくもなった。だがわたしは叫びもせず呪いもかけず、あまつさえ、何ひとつの努力もしないでいる。売れっ子の真似すらしない。わたしにYouTubeのまめな更新なんかできるわけがないし、タレントまがいの仕事をやれる技能もない。とどのつまりは、売れてチヤホヤされている人が羨ましい、でも努力はしたくない、という念がわたしに充満しているだけなのである。きっと、わたしが今すぐ消滅するだけで、世界の幸福度指数は上がるのであろう。邪魔者が誰なのかは、このテキストを今読んでいるあなたには明白であろう。このテキストからあふれる醜悪さがわたしそのものである。
しかし、昨今はそんな風にわたしの心を淀ませる人気者たちがコンスタントに炎上してくれるので、とても小気味がいい。ストレス解消になる。金儲けのことばかり考えて、ほかの重要なことに頭を回せないからこんなことになるのだ。ざまあみろも甚だしい。夕飯のおかずが一品増えたような気分。ついでに全然面白くない怪談本を出して作家ヅラしている若輩どもも不幸な目に遭ってくれないだろうかと考えながらのある日、気分よく鼻歌を響かせて近所をぶらぶらしていたところ、ふと見慣れた大学病院の形が変わっていることに気がついた。
通常なら「右に折れたり左に折れたりする建て増しされた直方体の連なり」とでも表現できそうな大学病院の形が、どこか丸みを帯びていたり目を凝らすとポツポツと穴が空いていたりしており、敷地の奥行きが無限に続いているような雰囲気を醸しだしている。
怪訝のレベルを僅かに超えた感情で立ち止まり、じいと見ている間、ずっと大学病院はそんな感じだった。大学病院が狂ったのか、それともやつがれが狂ったのか、もしやつがれが狂ったのならば目の前に大学病院があるのだからこれは話が早い。しかし、こんな変な大学病院に通っていては殊更に狂いが進むのではないだろうか。いくらかその光景に囚われてはいたが、結局は「ま、そんなこともある……」と独りごちて、わたしは踵を返すことにした。実家は近い。気持ちを切り替えて母上の顔でも拝み、トンカツをおねだりしようかと目論んだ。青い平皿に山盛りのキャベツと黒豚のトンカツ。脳裏に浮かんだだけで思わず指をパチンと鳴らしたくなるような夕飯だ。実家に入り、携帯電話をふと見たところ、借金取りからの着信が三件ほど残されていた。下足の状況から判断するに母は出かけているようで、ときどき父が二階の居間を歩く音を聞きながら、キッチンでコーヒーを飲み、タバコを吸った。
はぁ、と溜め息が出た。
もしかしたら自分は、ついさきほど邂逅したあの奇妙な大学病院にやはり行くべきだったのではないだろうか。もう世界が狂っていると決め込むのはやめて、しっかりと自分が狂っていることを受け入れる時期が来ているのではないだろうか。
穴が空き、丸みを帯びたあの病院はまるでチーズのようだった。
チーズの病院での入院生活はどんなものだったのだろう。
ねずみのナースが点滴を打ったり、食事を持ってきたりしてくれるのだろうか。
ねずみのお医者さんがわたしの頭を見てくれるのだろうか。
ねずみのお医者さんは、きっといつかわたしにこう言ってくれる。
「よく頑張りましたね。寛解しましたよ」
ねずみのナースが目に涙を浮かべて花束をわたしに渡す。
ねずみの祝福を受けて、わたしは次の世界を歩もうとする。
その世界にはきっと恨みも妬みもなく、真摯な努力と優しさだけが溢れているのだろう。
わたしは折角わたしの存在が許される世界を見かけたのに、そこに行かなかったのだ。
翌日の大学病院はいつもと変わらず、わたしもまた、いつもと変わらなかった。
- ホーム
- ねずみのお医者さん
- コラム・インタビュー 新世界
- ねずみのお医者さん