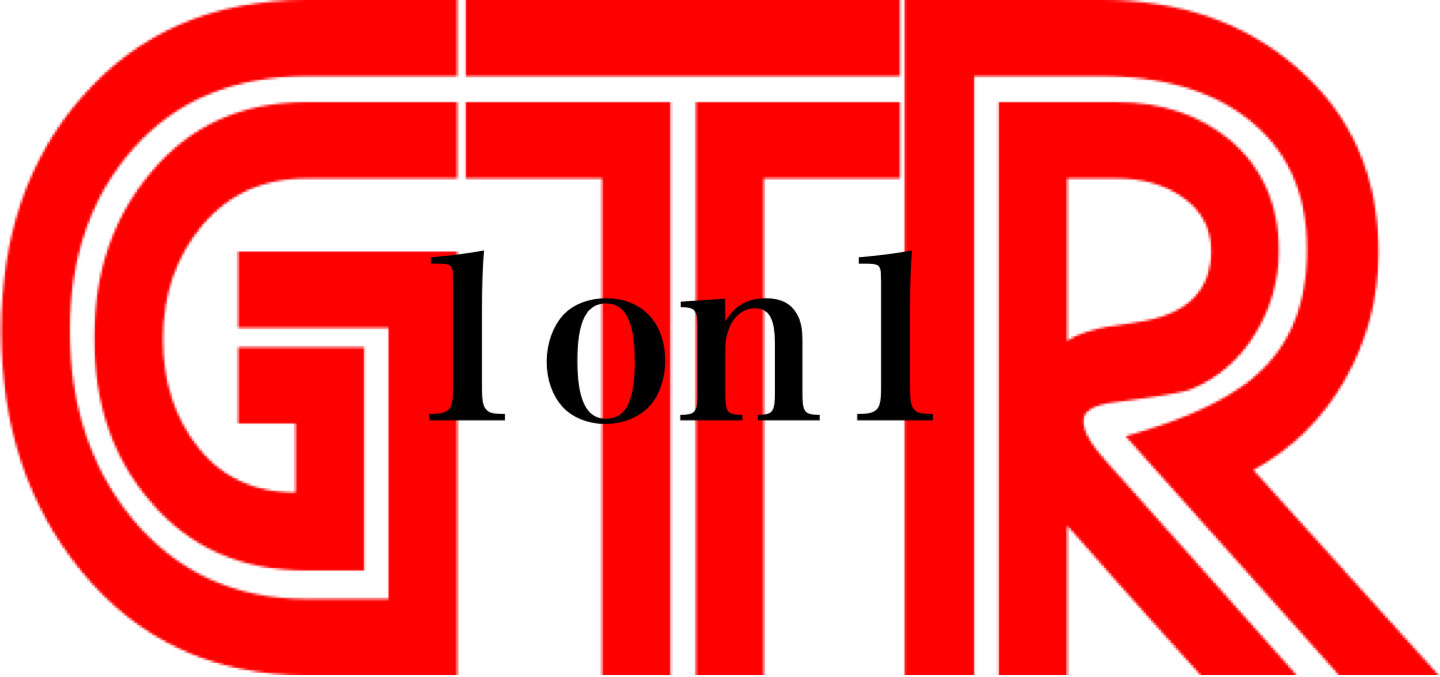終戦直後の混乱の中で、サチは山間の小さな集落に生まれた。
食糧難だったこの時代、男手のなかったサチの家はあばら家と呼ぶにふさわしい貧相なもので、日々の生活は貧窮を極めた。
加えてサチの住む地域は雨が少なく土壌も悪い。痩せた田畑で育ったわずかながらの米も、ほとんどが国への供出に回り、自分たちの食料は自ら調達せねばならなかった。イナゴは貴重なカルシウム源で、水田のタニシはご馳走だった。醤油や砂糖は手に入らず、渋いだけで甘みのない小さな木の実を四人のきょうだいと分け合った。時々獲れるスズメは乾燥させて保存食にしていた。
その頃の思い出といえば、空腹の辛さと上空を飛ぶ米軍機の音、そして村で頻繁に行われた誰かの小さな葬式だった。
葬式にはまだ幼かったサチの弟のものもあった。満足に食べ物を得られず、栄養失調で骨と皮だけになった弟は、腹を満たす幸せを知ることなく、ある夏の朝にその短い生涯を終えた。
弟の小さな亡骸は、裏山の共同墓地へ割った食器と共に埋葬された。
野犬に掘り返されぬよう出来るだけ深く穴を掘る。弟を土の底に横たえる際、それまで呆けたようにぽかんと口を開けたまま、虚空を見ていた母がぶるり、と一度だけ肩を震わせた。直後、獣の咆哮のような低く掠れた叫び声をあげて、弟の名を呼び咽び泣いた。母の哀哭は蝉の声と混じり合い、青く抜けた初夏の空へ吸い込まれて消えていった。
十代の半ば、生活は相変わらず酷く苦しいものだったが、サチは自分の将来についてぼんやりと考え始めた。サチにとっては小さな村の生活がそれまでの人生の全てであり、自分はここで死んでいくのだ、そんな漫然とした思いだけが胸中にあった。明日の見えない暮らしの中で、知らず知らずのうちに諦めと達観が痩せた体に染みついていた。終戦と共に米軍の爆撃に怯える日々は終わった。「一灯でも光を漏らすな」ときつく言いつけられ、暗がりで怯えながら食事をする必要もない。なのに、未だ心は暗闇の中にある。
なぜにこれほど苦しいのか。なぜにこれほど不幸なのか。生まれ落ちたその日からこの身の不幸は始まっている。地獄はどこまでも地続きで、死の影はサチのいつもすぐそばにあった。
村の裏手に「それ」はあった。
大通りから横道に逸れ少しばかり進むと雑木林がある。鬱蒼とした樹木に囲われた林を抜けると、見晴らしのいい高台があり、村を見下ろす形で「それは」立っていた。巨躯に茂る葉はその身に風を受けるたびにざわめき、まるで姿の見えないたくさんの生物が、一斉に騒ぎ出したかのように聞こえた。サチにはそれが恐ろしかった。
村の者たちは皆、ことあるごとに足しげくそれの元に通い、わずかながらの食料を丁寧に供えた。膝をついて目を閉じ、手を合わせ願うと必ず願いは成就すると信じられていた。いつの頃からか分からないが、代々丁重に扱われているものなのだ、と母に聞いたことがあった。
「神様は弱い者と貧しい者を助けてくれる」
母はよくサチにそう語りかけた。しかしサチにはその全てが嘘っぱちであるということが分かっていた。どんなに願っても、可愛い弟はあっけなく死んだ。戦争が終わり、帰ってくると信じていた父のことも、とうの昔に諦めていた。「それ」がサチの願いを聞き入れてくれたことは一つもなく、サチにとっては信仰の対象などではなく「畏怖すべきもの、恐ろしいもの」でしかなかった。サチがそれを恐れる理由は、そのおぞましい外形にもあった。
ちょうど真ん中、目線の高さに〈人の顔〉がくっきりと見えるのだ。模様がそう見せるものではない。はっきりと浮き上がった年老いた女性の顔。一文字に口を結び、瞼(まぶた)は固く閉じている。苦悶に満ちた老婆の顔がいつもあった。なぜそんなものが浮かんで見えるのか見当もつかなかった。
ある年の夏。元々雨の少ない地域ではあったが、その年は輪をかけたように深刻な水不足が続いていた。干上がった田畑では作物が激減し、前年からの備蓄もあっという間に食い尽くした。
ひっ迫した村の危機的状況に大人たちは会合を開き、村民全員で裏山のそれの元に訪れ手を合わせて祈った。その願いが通じたのか、その日の夜にはさざれ雨が降り始め、みるみるうちにひび割れた田畑が水であふれた。
神か仏か、窮地を救った何かに向かって村民たちは涙を流し口々に感謝を告げた。
そんな出来事があってから、村民は前にも増してそれの元へ足を運ぶようになった。
サチの母も例外ではなかった。
ある朝、サチは畑で採れた僅かばかりの痩せた野菜を供えてくるよう命じられた。内心一人であそこに向かうのは気が引けたが、半ば強引に押し付けられる形で玄関を追い出された。カゴを抱えて裏山を登り、汗をぬぐいながら平べったい石の上に野菜を並べると、高く昇った陽が痩せたサチの背をじりじりと焦がす。汗で張り付いた汚れたシャツにうんざりしながら、かがんで手を合わせた時だった。
みちみち。
みちみちみち。
ゆっくりと、樹皮を爪で剝ぐような妙な音が頭上で響いた。驚いて顔を上げると同時に尻もちをつく。
樹皮が蠢いている。ちょうど顔のある部分だ。浮き出た顔が音を立てながらゆっくりと少しずつ形を変えていく。あっという間に形は変わり、我に返った頃には、先ほどまでとは全く〈別の顔〉が浮かんでいた。
ぶるぶると震えながら変化を見届けたサチは、弾けるように駆け出し、山道を転げ落ちそうになりながら玄関までたどり着いた。土間に立つ母に今見たものをまくし立てると母は手を止め、こともなげにサチに告げた。
「あぁ、小寺の婆さんが死んだけえ」
小寺の婆さんとは——同じ村に住む九十歳に近い老婆だ。最近はほとんど姿を見かけていなかった。最後に見かけたのは昨年の暮れか。痩せて骸骨みたいな顔を思い出した時、樹皮に浮かんだ苦悶の表情が、一体誰のものなのかはっきりと分かった。
その時に母に告げられた言葉は、まるで呪詛のようにサチの脳裏に焼き付いた。
この村で生きて、死ぬ女はみんな神様になる。
入れ替わって役割を回すんよ。
叶える側に回るんよ。
だけん、生きてるうちに沢山、神様にお願い事しなさいよ。
神様——。その言葉を思い出すたびに、あの日見た樹皮の蠢きが脳裏に浮かびサチは身震いした。
それからほどなくして、サチは結婚して嫁ぐために村を出た。
「ナツ」という名の三つ歳の離れた妹は、サチが村を離れるその日まで、姉の門出を心から祝福しつつ、寂しがって泣いてくれた。
「あんたも必ず幸せになりぃよ。泣くな、美人が台無しじゃ」
サチが微笑みかけると妹は涙をこらえながら、くしゃくしゃな笑顔で何度も頷いた。
ゼロからの出発でサチの第二の人生が始まった。わずかながら貯まった金でミシンを買い、近所の人達の洋服の仕立てをする仕事を細々と始めた。生活の安定にもいくらか目途がついた。村を離れた二年後には長男が生まれ、新しい人生に明るい光が差してきた。
そんなとき郷土の母から連絡を受けた。その時のことは生涯忘れることはできないという。
小さく震える声で母に告げられた内容は、にわかに信じがたいものだった。
「ナツが死んだ」
年ごろを迎えた妹にも想い人が出来た。しかし、様々な理由で妹の願いは叶わなかった。添い遂げられないことに絶望し、悲嘆した妹と想い人は、ある晩そろって裏山へ向かった。そして、持ち出した包丁で互いの喉を掻き切った後、大樹の下で抱き合うように事切れていた。
妹の訃報を聞いた時、サチは受話器を握りしめ泣き崩れた。薄倖な生涯を閉じた妹の無念を思うと、身を裂かれる程苦しかった。そのあとも幾度も妹を想い涙を流したが、そのたびにあの母の言葉が頭に浮かんだ。
この村で生きて死ぬ女はみんな神様になる。
そうやって役割を回すんよ。
叶える側に回るんよ。
だけん、生きてるうちに神様に沢山、お願い事しなさいよ。
神様。神様。神様。何一つ願いを叶えないものの何が神だというのか。神も仏もあの村にはいない。
あるのは妹の無念と、飢餓によって奪われた幼い弟の魂だけだ。
妹の死から数年したある夜、村の大樹に何者かが火を放った。
村人が寝静まったあとの犯行であったため、近くの住人が異変を発見した頃には手の施しようが無いほど燃え上がっており、完全に燃え尽きるまで村人たちは、業火に包まれて死にゆくそれを、ただ呆然と眺めるしかなかった。
その後、警察の介入があり捜査が始まったが、村の内部犯行であることは明白だった。犯人には最初から目星がついていた。しかし誰一人として頑なに真相を話さなかった。加えて被害がその一件のみであったこと、人的被害はなかったことで早々に捜査は打ち切られた。
火を放った犯人が誰か、サチにも最初から分かっていた。
しかし村の住民と同じように、その生涯において、決して誰にも話すことはなかった。
神様——。誰ともなく呟き、病室の窓の外を見る。
もうすっかりと陽の長くなった夏空と太陽が、老いたサチの頬をそっと優しく照らしていた。
「怪露」(2023年発行より転載)