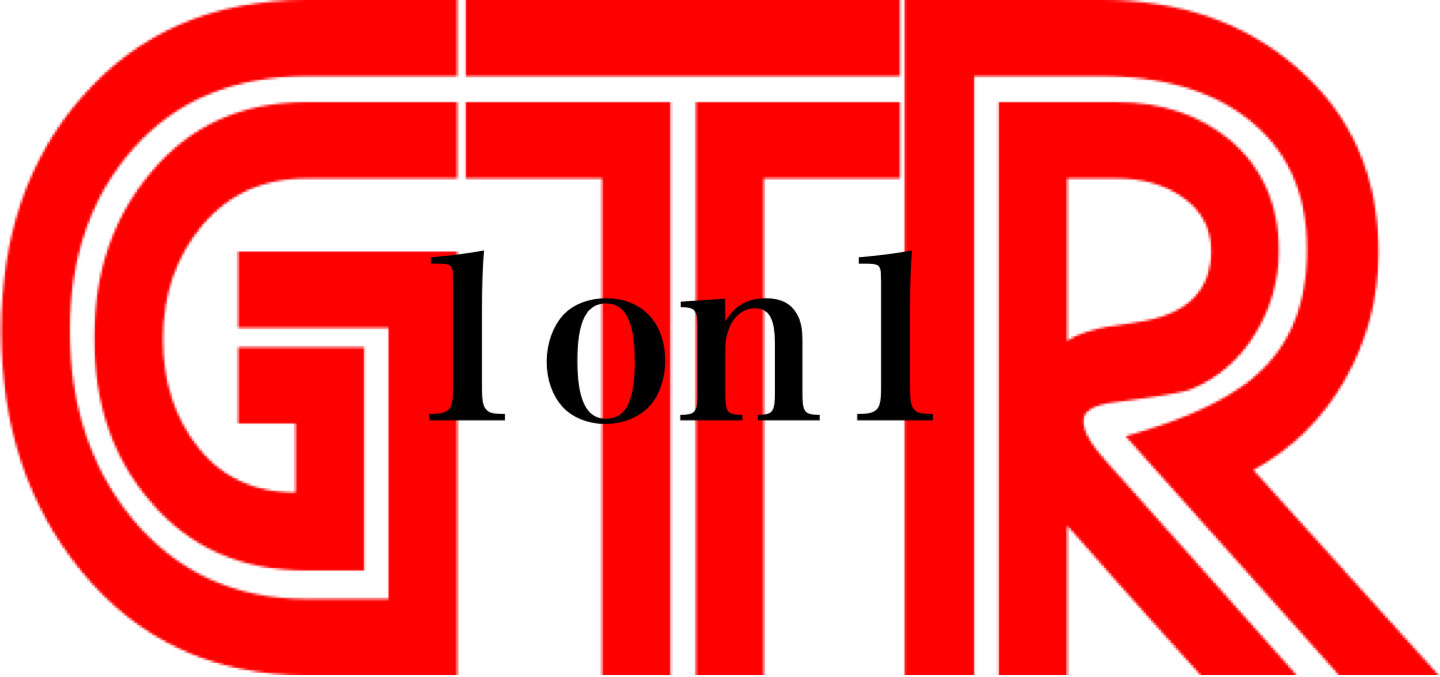シーンで活躍する怪談語りを深堀りするインタビュー企画「怪談語りがたり」。
4回目は住倉カオスさん。
怪談番組MC、イベントオーガナイザー、作家、ギタリスト、猥談家など様々な肩書をもつ彼の物語とは?
(インタビュー・写真●怪談ガタリー編集部)

怪談最恐戦
——2018年「怪談最恐戦」が始まりました。立ち上げた当時はどんな思いがあったのでしょうか?
「その当時怪談カルチャーはまだアマチュア文化が色濃くて、俺はプロが生まれたら良いなと思ってたのね。そういう動きがあれば、お客さんももっと広がっていくんじゃないかなって。で、オープンで公平で誰でも参加できるフェアな怪談の大会を企画して。ちょうどその時に本を書いていた竹書房で『それ、イベントにしましょう』って事になって、竹書房といえば『麻雀最強戦』が有名だからタイトルはもうそのまま『怪談最恐戦』に」
——誰にでもチャンスがあって、プロが生まれるきっかけになる……特にここ数年は最恐戦をきっかけに活動を始めた方々が多くいらっしゃいますよね。
「そうだね。誰でも参加できるのでプロもアマチュアも関係なく、参加するハードルは低いけど、上り詰めていくにはめちゃくちゃ厳しい道で、簡単なことでは上にはいけないハードルの高いものが必要だと思って。それで、時間制限だったり、審査員だったり、ルールを細かく厳しいものに設定していったんですよね。裾野は広く頂きは高く」
——もっとも気をつかったところはどんなところですか?
「審査方法と審査員の人選は一番気をつかったね。怪談の番組を持っていたり、キャスティング権のある人を入れて、一般にアピールするために怪談の裾野を広げたいから、怪談ファンじゃない人が聞いてもいいと思うものが選ばれたらなと。毎年ちょっとずつブラッシュアップして、途中から一般投票も入れたんですけど、人気投票にはならないように考えてましたね」
——そんな怪談最恐戦6大会を経て、今の怪談カルチャーを住倉さんはどう感じてますか?
「いろんな人がいろんな楽しみ方をしてて、すごくいいと思いますね。2018年当時よりもカルチャーの規模は確実に大きくなっていると思うので。それが最恐戦に参加してくれた人や、観に来てくれた人のいろんな羽ばたきが複雑に絡み合ったバタフライエフェクトであれば、とても嬉しいし、一つの役目を終えた気分ですね」

これからのこと
——今後の活動や展望など伺えたら。
「最恐戦があることによって、オーガナイザーは公平じゃなきゃいけないっていうのをすごい思ってたんですよ。作家活動やイベント出演・企画とか、ちょっとどこかでためらいがあって。赤外線の装置つけて心霊スポット行ったりとか、そういうのもまたやってみたくなったんだよね。怪談に対しても民族学的・ノンフィクション的なアプローチに自分は立ち戻ろうと思ってて。最恐戦をやってて思ったのは、新しい怪談語りのカタチ、自分に合ったスタイルをみんなが模索してて、俺も個人の活動にまた改めてフォーカスしていきたいなって」
——改めて怪談と向き合うフェーズなのかもしれませんね。
「また現場に行って取材するっていうことに立ち戻りたいのと、自分の思う怪談表現というか、語りの表現って、人の想像力を刺激するものだと思ってて。語りの技術よりも、全体のムード、五感の相乗効果で人の心を揺さぶるものを作りたいと思ってます。舞台芸術としての怪談は常に気になるところではあるので。映像、音楽、そして演出……あと、怪談を解体していくと言葉になっていくじゃない? その言葉の力をポエトリーリーディングというアプローチで融合していくのが、いま自分の中の一つの大きなテーマですね」

——怪談と音楽の親和性について、住倉さんの中ではどう感じていらっしゃいますか?
「すごくあると思いますよ。歌舞伎とかでも所謂『ヒュ~ドロドロドロドロ~』とか、怖い感じで実際人の心揺さぶったりするじゃない。でも実話怪談においては『BGMが邪魔だ』と嫌われる傾向も割とあって。それって単なるBGMでしかないからじゃないかな? と。言葉と音は、もっと緻密に融合できると思うのでその可能性を探りたいし、そのためには言葉も音楽も、その場で生まれてないとダメだと思うんだよね。BGMってのはポン出しするじゃない。でもそれってどこの会場で流れて、どういうお客さんが聞くかっていうことは全然想定されてない。だけど、怪談の場っていうのは、聞く人もいて初めて生まれてるものだから、それをやるには即興音楽でないとちょっと難しいのかなと。例えば、演奏者が怪談(言葉)を聞きつつ、ここは音を下げる瞬間とか、ここはちょっと不協和音を出してみたくなる時間とか。そしてなにより怪談(言葉)を聞かせないと意味ないから、語り手も音を聞いて、このセンテンスもう一回言ってみようとか……そういう表現の可能性を追求してみたいですね」
——響さんとのユニット「オカルトロニカ」などが、まさにその活動の一線にいらっしゃると思います。
「体験としての怪談。『今ここにいれて幸せだった』という思いを持ち帰ってもらえるような、そんなイベントがやりたいですね」

怪談とは
——今後の怪談カルチャーに思うことは?
「楽しんでくれる人が増えるということに関しては、常に思いはあります。まだ怪談、特に怪談イベントとかに触れてないような層に、そういう楽しみ方があるっていうことを広げていきたくて最恐戦とかもやって。ただ実話怪談・現代怪談って、結構理不尽な部分が怖いっていうことが多いじゃない。例えるならホラーブームでホラー映画の表現が、複雑化していくような過程だと思うのね。エンタメとしての面白さ、興味深さはどんどん上がっている。だけど本質的な『なぜ人は怪談に惹かれるのか?』というところをちょっと後回しにしすぎてる気もしてて。俺の怪談のベースはやっぱりおばあちゃんが囲炉裏で、『山でこういうことやるとこんな怖いことが起きるから、山に一人で行っちゃいけないよ』っていう戒めの話というか。それを子供が聞いて怖がるっていうのが怪談の原風景だと思うの。そこからどんどんと離れているんじゃないかなって。まあ、頭が固いだけかもですが(笑)」
——大切なことだと思います。
「この語り口、切り口、構成がいい。新規性がある。みたいなのは本質ではなくて、俺にとって怪談は知的好奇心なんだよね。そういうとこに立ち戻っていく人も増えていって欲しい。承認欲求とか自己顕示欲のためのものでない怪談に立ち戻っていく人たちが、ちょっとずつでも増えて欲しいなって。『人が死んだら魂ってどこに行くの? 霊ってほんとにいるの?』そういう切り口で怪談に目を向ける流れも来るんじゃないかなと。今の七十代、八十代の人は団塊の世代で。お金を稼ぐことで豊かな生活をすることが幸せだと思ってた世代の人たちが、実際に自分が死ぬっていうことをリアルに考えるようになって『死ぬときに何が残っていくんだろう?』ということを思うときに、もしかしたら怪談の役割があるかもしれない。それはもう怪談ブームとかを越えて『日常の中で怪異を語る』という行為がある。そんな世の中が来るかもなって」

——スピリチュアルや霊感商法などへのリテラシーもより一層必要になりますね。
「そうだね。あと、戦後百年近くになって、戦争を知ってる人たちがどんどん減っていく。その中で、当時の話を集めたり伝えたり、災害もそうだよね。もともとそれの役割は文学だと思ってるけど、『はだしのゲン』が図書館からなくなっていく中で、怪談が寄り添い、語り継いでいけるものもあるんじゃないかな……僕はカメラマンとかやってたし、機械も好きだったりしてすごくリアリストで魂とか幽霊とか全く信じてなかったんだよ。ただそれが心霊事件なんかに触れるたびに少しづつ違和感が出てきて。で、決定的なことがあって」
——なにがあったんですか?
「四十歳くらいで出版社での不摂生がたたって心不全になっちゃって、手術の時に『万全を尽くしますが死ぬリスクはゼロではないです』ってお医者さんに言われて。それで『死ぬのかなぁ? なんかやり残したことあるかなぁ?』って考えたら、それまで好き勝手に生きてきたから、何も未練がなかったんだよね。でもたった一つだけ『あぁ、死ぬまでに犬を飼ってみたかったな』って思って。幸いにも手術は成功して、その時に『あ、俺って犬を飼いたかったんだ』って気づいて。もう一回本当に死ぬ時にまた『あぁ、犬を飼いたかった』って思うのはなんか自分が可哀想だと思って。子供の頃はドリトル先生とかの影響で動物が大好きだったんだけど、大人になってすっかりそんなこと忘れてたから。それから犬を飼うことをすごい意識して、いつ出会いがあっても良いように、犬が飼える物件に越して、犬もいないのにしつけの教室に通って(笑)。そしたらある日、保護犬の子に運命的に出会って。それがモグなんだけど。出会った瞬間に、今まで自分の心には犬の形をした穴がぽっかりあいてて、モグと出会ったことでその穴が埋まった気がして。『今初めて一人の人間になったんだぁ』って感じて。それからモグと楽しい日々を過ごすんだけど、モグは元々病気を持ってて八年二か月で見送ることになって。ただペットロスというか、肉体がないからもちろん悲しいは悲しいんだけど、モグの存在は自分の深い部分で感じるんですよ。『あ、魂って本当にあるんだ』って。それで、まぁ勘違いかもしれないけど『死が終わりじゃない』って普通に受け入れられるようになりましたね」
——住倉さんの人柄と死生観が詰まったエピソードですね。
「人は生まれて、死ぬじゃない? その死んだ後のことが怪談で、生まれる前のセックスっていう行為が猥談。だから、俺の中では死から生まれるまでのミッシングリンクを繋ぐのが怪談と猥談なんです」
生と死、死と生の円環を結ぶミッシングリンクを、インプロビゼーションで紡ぐジャジーでブルージーな男……それは住倉さんがかつて憧れた、大人の男像そのものだと感じました。
住倉さん、貴重なお話をありがとうございました。