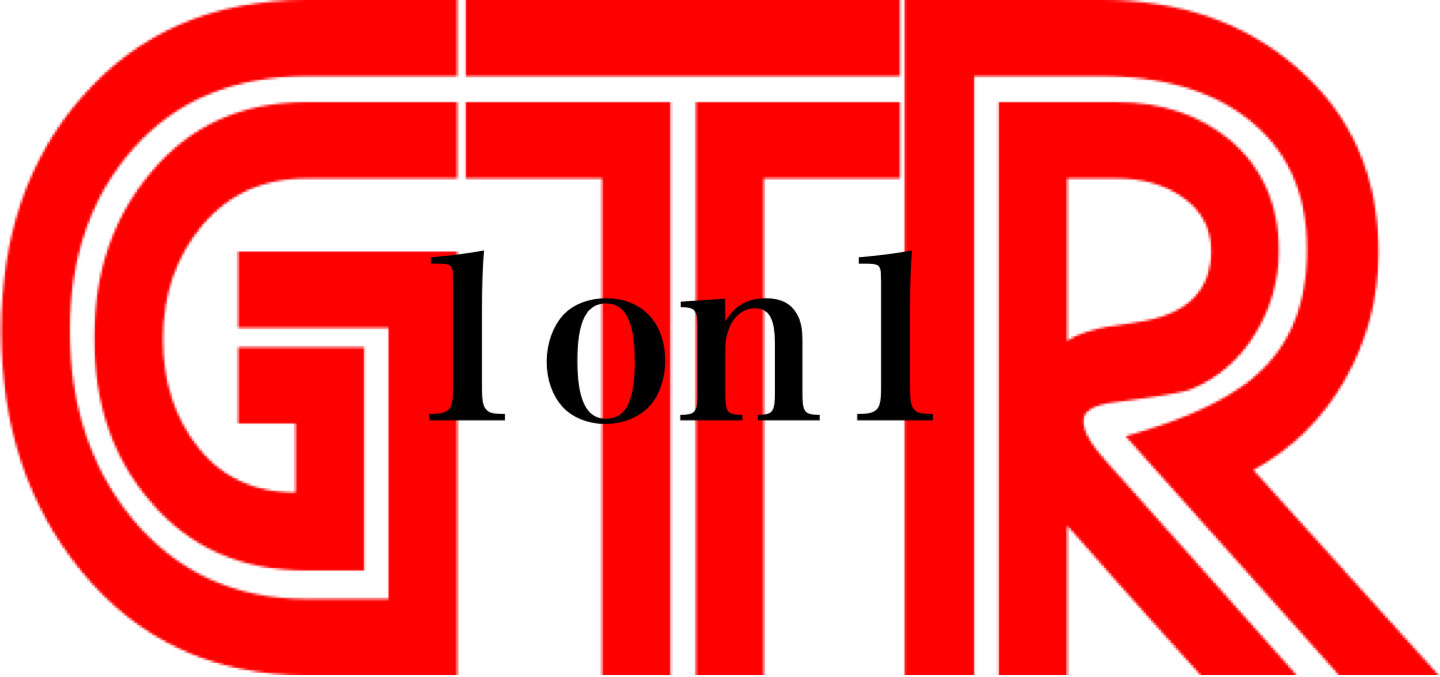十歳になった年の夏休みだったと、恭平さんは言う。「その子」のことを三つ下なんだ、と思ったから間違いないと。恭平さんの父親は建築士で、当時は地元の大きな工務店の設計課にいたという。現場に出ることも多く残業や休日出勤が常態の職場だったそうで、子供の頃、親父にどこかに連れて行ってもらった記憶は殆どない——恭平さんは回想する。
「土曜日に知り合いの家でお誕生会をするんだが、恭平にも来てほしいんだ」
夕食の席で、父は唐突に言った。
「お誕生会?」恭平さんは聞き返した。寡黙で厳しい人という印象を抱いていた父から、そんな子供っぽい、可愛らしい言葉が出たのが意外だったという。
「ああ。七歳になる女の子のお誕生会なんだ」
来られなくなっちゃった子がいてね、その子の代理を頼みたいんだよ——そう答えた父が、目を伏せていたのが気にかかった。
向かいに座る母が、無言で父を睨んでいるのに気づいた。その前の晩、両親がリビングで何事か口論していたのを、恭平さんは隣の寝室で夢うつつに聞いていたそうだ。
不穏を感じはしたが、父と久しぶりにどこかへ出かけられるのは嬉しかったし、まだ十歳の少年にとって「お誕生会」という響きはやはり特別なものだった。
恭平さんが快諾すると、父はほっとした様子で「じゃあ、朝の七時に迎えが来るから」とだけ言って、食事を半分以上残して席を立ったそうだ。
土曜日の朝。スーツを着た父に六時に起こされ、玄関先で一家で「迎え」を待った。不安げに見える母に「お母さんは行かないの?」と尋ねたが、ただ首を振られたという。
迎えの車は、側面に父の会社の名が入ったワンボックスカーだった。運転席から黒スーツの若い男性が降りてきて、両親に一礼してドアを開けてくれた。
乗り込むと、何か生ぐさい匂いが鼻を衝いた。車内にはふたり、膝にホールケーキの箱を載せた老人と、恭平さんの母より少し年上だろうか、化粧けのない地味な女性が座っていた。彼らもスーツ姿で、「女の子のお誕生会」という語から想像していたより堅いイベントなのかな——と恭平さんは戸惑ったという。
恭平さんに次いで父が乗り、車が発進すると女性がこちらに話しかけてきた。
「そちらが息子さん? ごめんなさいね、今日はうちの子の代わりに」
どうやら本来は彼女の息子が「お誕生会」に行くはずだったのだが、部活中の事故で足を折って入院してしまい、急遽その代役が恭平さんに回ってきたということらしい。
「××さんに同い年のお子さんがいて本当に良かった」
女性はしきりにそう言ったが、誕生会に代理を立てるのも、それを年恰好で決めるというのも考えてみれば変な話だった。
変と言えば——ワンボックスカーが進む道のりにも違和感があった。車窓からの景色に、「わざと同じ場所を何度もぐるぐる通っているのではないか」と思っていたらしい。
だから目的地に着くまで二時間近くかかったそうだが、本当はその「家」は三十分もかからない、恭平さんの家と同じ市内にあったんじゃないかと彼は想像している。
いかにも関東の郊外らしい新興住宅街の一角で、大きな道路に面して櫛の歯状に私道が伸びて、それを取り巻くように左右三軒ずつ建売住宅が並んでいるというつくりだった。
だが、その「家」の区画だけは、他に家はなく雑草が茂った更地に囲まれていたという。
一同は車から降りた。曇っていたが、湿気が肌にまとわるような蒸し暑さを感じた。
父がバックドアを開けて、黒い染みの飛んだクーラーボックスを重そうに抱えてきた。
一見して変な家だったそうだ。というのも、白い漆喰の壁のどこにも窓がなかったというのだ。のっぺりした、ボール箱のような建物。
正面に玄関だけがあって、大きな懐中電灯を手にした黒スーツの運転手が、鍵を差し入れてドアを開けた。中は真っ暗だった。
お誕生会があるのに、どうして施錠されていて灯りも点いてないんだ? いよいよ恭平さんの中で、違和感が確信に変わったという。
運転手の懐中電灯を先頭に、大人たちは三和土を無視して土足で家に上がっていく。
「玄関はそのままに」一番後ろで、ドアを閉めようとしていた恭平さんは父に制止された。
家の中には、何とも言えない悪臭を帯びた熱気が満ちていた。汗が湧き、背中にシャツが貼りつくのが不快だった。廊下を抜け、リビングらしき広い部屋に入った。「らしき」というのは、テーブルとかソファとかテレビとか、そういったそれらしい調度品が一切なく、傷みのいったフローリングの中央に、血が固まった瘡蓋に似た汚れがあちこちについた、大きな金盥のようなものが置かれているだけだったからだ。
こんなところに人が住んでいるはずがない。
説明を求めて父にすがろうと探した。父は、懐中電灯の灯りが床と背中を白く照らす中で、クーラーボックスの内容物をどろどろと盥に明けていた。車の生臭さの原因が分かった。それは大量の、魚の頭とはらわただった。
老人が箱を開いてケーキを盥の横に置き、震える手でマッチを擦って一分ほどもかかって七本の蠟燭を灯した。
「かなえちゃん! お誕生日おめでとうっ!」
運転手が天井に向かって叫んだ。闇の中で、大人たちが口々に「おめでとう!」と声を上げ、やけくそのように震える声でハッピーバースデーを歌っていた。
ハッピーバースデー トゥーユー ハッピーバースデー トゥーユー
運転手の声も裏返って聞こえた。
「今年も良い子にしていたから、おじいちゃんとお父さんとお母さんとお兄ちゃんがお祝いに来てくれたね! 嬉しいね!」
そうだ、確かに僕たちは家族みたいだ——恭平さんがそう思った瞬間だった。
どん どん どんどんどん
天井から、何かが近づいてくる——足音のようなものが聞こえた。
まずは、ぱんっという音とともにあたりが真っ暗になった。懐中電灯の電球が弾けたらしかった。そして、ぐじゅりと水気を帯びた音。ケーキが上から、何かに凄い力で圧し潰されたのを想像したという。
「出ますっ!」
運転手が叫んだ。
父が恭平さんの手を掴んで、玄関を出るまで引っ張ってくれた。背後でずっと、壁を叩くような鈍い音が続いていたという。
外に出て、恭平さんは驚いた。中にはほんの十分ほどしか居なかったはずなのに、陽が黄色味を帯びて陰りつつあった。
大人たちは言葉もなく車に乗り込んでいった。ダッシュボードの時計を見ると、もう夕方の五時を回っていた。
「……悪かったな恭平、こんなことに付き合わせて」
車内の重い、困憊したような沈黙を破って父が言った。
「今年で俺たちは御役御免だから」
また二時間かけて戻り、玄関先で待っていた母に安堵の笑顔で迎えられたその夜。父に誘われて恭平さんは一緒に風呂に入った。それを二人きりで、あの家について聞いて良いという合図だと理解して、恭平さんは訊ねたそうだ。アレはなんだったの——と。
「地鎮祭……って言っても分からないか。おまじないみたいなものなんだ。あの家には七歳の女の子が居て、毎年その七歳の誕生日をお祝いしてる。そういうことになってるんだ」
じゃあずっと、七歳のお祝いなの? 去年も、来年も? どうして?
父は困ったように笑ったという。
「そりゃ……いつまでもまだ七歳の子供だって思っててもらわないと困るんだろ」
あれ以上大きくなっちゃったら、手に負えないだろうしな。
宿屋ヒルベルト
本業は編集者。
仕事でのリサーチをきっかけに本格的に怪談蒐集を開始。
初の著書『怪の帖 美喰礼賛』が8月29日発売。